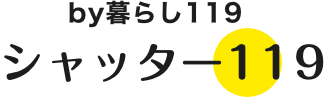防火シャッターの法的点検義務と罰則を徹底解説
修理・交換2025.05.18
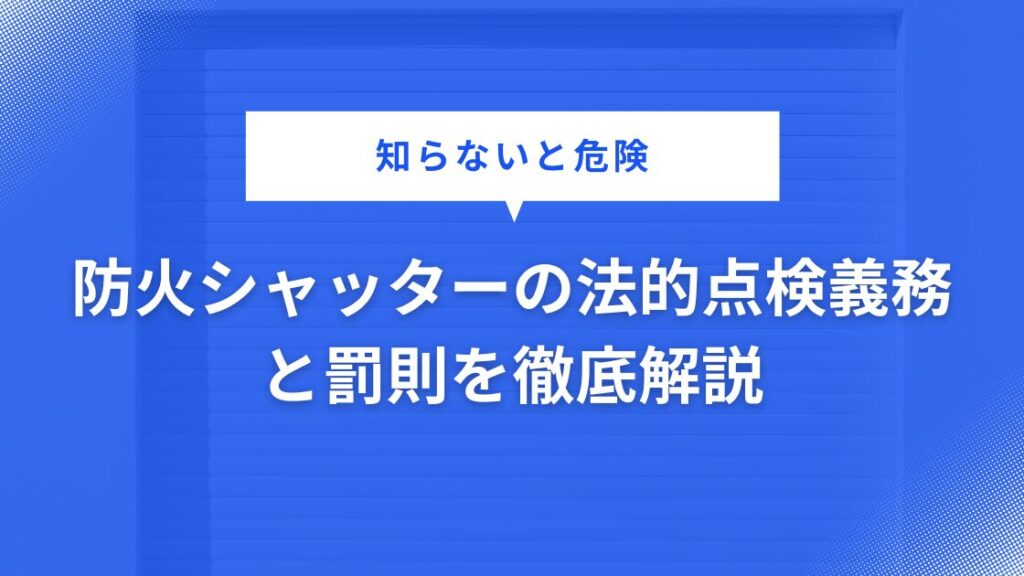
「火災時に延焼を防ぐための防火シャッター。実は、年に一度以上の点検と行政への報告が法律で義務付けられていることをご存じでしょうか?」
こうした法定点検の存在を知らずに、「消防点検だけはやっているけれど、防火シャッターはノータッチ…」という管理者の方も少なくありません。
しかし、いざ火災が発生した際に防火シャッターが正常に作動しなかったとなると、被害が拡大する危険性が高まります。
さらに、定期点検を怠っていると建築基準法に違反し、罰則や行政処分の対象になる可能性もあるのです。
本コラムでは、関西エリア(大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀)で店舗や工場、倉庫などを管理している皆様に向け、防火シャッターの点検義務とその背景、具体的な点検項目・頻度、罰則などをわかりやすくまとめました。
最後までご覧いただき、法令順守と安全対策の両面から、確実な点検・報告を行うためのヒントをつかんでください。
防火シャッターとは?
まずは「防火シャッター」という設備を簡単におさらいします。
通常のシャッターと違い、防火シャッターは火災時に高温や炎を遮断し、延焼を食い止めるための耐火性能を備えています。
ビル内部やテナント間の区画に設置され、火災感知器と連動して自動でシャッターを閉鎖するしくみになっているものが多いです。
1.火災時の延焼拡大を防ぐ役割
火災が建物内のどこかで起きたとき、防火シャッターがしっかり作動すれば、火や煙が隣接スペースへ広がるのを抑え、人命や財産を守る確率が格段に上がります。
特に商業ビルや大規模施設では、不特定多数の人が利用する空間が広くつながっているため、火災が起きると被害が一気に拡大しがちです。
そのため、劇場、病院、飲食店、ショッピングモールなどでは防火区画の要として防火シャッターが設置され、火災発生時に自動的に閉まるよう設計されています。
2.住宅用とは別物
住宅用に「簡易防火性能」をうたう窓シャッターなどもありますが、本コラムで解説するのは、建築基準法が対象とする業務用の防火シャッターです。
住宅の窓シャッターには必ずしも同じ法定点検義務が適用されるわけではありませんので、注意してください。
防火シャッターが法的に点検義務を負う理由
それでは、なぜ防火シャッターには定期点検が義務付けられているのでしょうか。
大きく分けると法令改正の経緯と、火災時の安全性という2つの背景があります。
1.建築基準法の改正
建築基準法第12条第3項では、一定規模以上の建物を「特定建築物」として指定し、1年に1回以上の定期的な建物検査を行い、その結果を行政へ報告しなければならないと定めています。
この制度自体は昔からあったのですが、2014年の法改正(2016年施行)により、防火設備(防火シャッターや防火扉など)も定期検査・報告の対象に加えられました。
これは、過去に防火シャッターが正常に作動しなかったことで拡大した火災事故の事例が相次いだため、防火設備の機能確保を徹底する必要があると判断されたからです。
2.重大火災事故の教訓
例えば2013年、福岡市内のある診療所で発生した火災では、防火区画のシャッターが閉まらず被害が拡大し、多くの犠牲者を出しました。
こうした痛ましい事故を受け、「建物に設置されていても、動かない防火設備では意味がない」という反省が高まり、定期点検の法制化が強化されたのです。
どんな建物が対象?~特定建築物と防火設備
防火シャッターの法定点検が求められるのは、一定規模以上の建物に設置されている防火設備です。
ここでは、建築基準法で「特定建築物」とされる主な例を挙げます。
1.特定建築物の例
- 劇場や映画館、集会場、百貨店、ショッピングモール
- 病院や老人ホームなどの医療・福祉施設
- 学校や図書館など公共性の高い建物
- 飲食店や物販店が入居する大規模テナントビル
- 工場や倉庫でも一定規模を超えるもの(人の出入りが多い業態など)
これらの建物は一般に、不特定多数の人が利用するため、火災時には大きな人的被害が想定されます。
そのため、防火シャッターを含む防火設備が正しく機能するかどうかを毎年チェックしなければならないのです。
2.どの防火シャッターが対象?
建物内部で防火区画として設置された「随時閉鎖式シャッター」や「感知器連動式シャッター」など、火災時に自動的に閉まる仕組みを持つものが基本的に対象になります。
倉庫の外壁に付いたシャッターなども、用途によっては防火区画扱いされているケースがあるので、施設全体の図面や設計者の説明を元に確認してみてください。
法定点検の具体的な内容と頻度
ここからは、防火シャッターの点検をどのように行い、結果をどう報告するかについて掘り下げます。
1.点検項目
国土交通省の告示で細かく定められていますが、代表的には以下のような項目を確認します。
- 動作確認:火災感知器と連動し、シャッターがスムーズに閉鎖するか。
- 障害物の有無:レールや開口部にゴミや荷物が置かれていないか。
- 機械装置の正常性:シャッターの駆動部(チェーン・ベルト・モーターなど)が劣化していないか。
- 非常電源のチェック:停電時にもシャッターが閉まるよう、非常用電源やバッテリーが正常か。
- 外観・設置状態:シャッター本体に歪みや損傷がないか、取付金具やレールに緩みがないか。
火災という非常時には1秒を争うため、この点検を怠ると、人命や財産を守れないリスクが高まります。
2.誰が点検できるのか?
防火設備(防火シャッター含む)の点検は、一級建築士・二級建築士または防火設備検査員の資格者が行う必要があります。
建物のオーナーが自分で「開閉してみただけ」では正式な点検とは認められない点に注意してください。
こうした有資格者が検査した結果を定期報告書として提出することが義務付けられています。
3.点検頻度
基本的に、1年に1回は防火シャッターを含む防火設備の定期点検を実施し、報告書を自治体の特定行政庁(建築主事)に提出します。
自治体によっては点検サイクルを独自に設定している場合があるため、自分の施設がある地域のルールを確認しましょう。
報告義務と罰則~点検を怠るとどうなる?
防火シャッターの点検を行った結果は、所轄の行政機関(市役所や都道府県庁の建築主事部署など)に報告しなければなりません。
ここでは、報告義務と、もし怠った場合のペナルティを解説します。
1.報告の流れ
- 資格者による点検実施:建築士や防火設備検査員が実際に施設を訪問し、防火シャッターをチェック。
- 結果をまとめた報告書作成:所定の様式に従い、設備の合否や不具合がある場合の改善計画などを記載。
- 行政へ提出:期限内に報告書を提出し、受理されれば完了。自治体によってはオンライン申請にも対応しているところがあります。
2.点検・報告を怠った場合の罰則
- 建築基準法の定期報告義務違反となり、最悪の場合は100万円以下の罰金や是正命令が科される可能性があります。
- 命令に従わない悪質なケースでは、懲役刑や法人への高額罰金など厳しい処分もあり得ます。
- 実際、行政が立入検査を行い未報告の違反を見つけるケースもあるため、「何も言われないから大丈夫」という考えは非常に危険です。
3.万一火災が起きたときの責任
法令違反だけでなく、点検不備が原因で防火シャッターが作動せず被害が拡大した場合、管理責任を追及される可能性が高いです。
損害賠償リスクや社会的信用の失墜を招く恐れもあるため、罰則という観点だけでなく、実質的なリスク管理の面でも定期点検は欠かせません。
点検義務にどう対応する?~実務的な流れ
防火シャッターの点検・報告義務をクリアするためには、具体的にどのように進めればよいのでしょうか。ここでは実務面でのポイントを解説します。
1.有資格業者への依頼
防火設備検査が可能な業者、あるいは建築士資格を持つ企業に定期点検を委託するのが一般的です。
消防設備の点検業者や建築物定期検査業者の中には、防火設備検査員が在籍しているケースが多いので、複数社から見積もりを取り、信頼できそうな業者を選びましょう。
▽ 依頼の流れ例
- 業者選定・問い合わせ:防火設備検査に対応しているか事前に確認。
- 見積もり・スケジュール調整:現地調査のうえで費用・日程を決定。
- 点検実施・報告書作成:シャッター含む防火設備を検査、所定の書式で結果をまとめる。
- 行政へ提出:オーナーまたは業者代行で提出。受理確認までをワンストップで対応してくれる業者も多い。
2.日常的な自主チェック
点検は年に1回でも、普段からシャッター周りに異常がないかを確認しておくと、定期検査時に慌てずに済みます。
例えば:
- 開閉動作の確認:定期的にシャッターを実際に動かし、感知器との連動や停止位置をチェック。
- レールや周囲の清掃:ゴミやほこりが溜まっていると動作不良の原因に。
- 物を置かない:シャッター開口部に荷物や商品を積んでしまうと、火災時の自動閉鎖が妨げられる。
こうした簡易確認を習慣化しておけば、点検前に不具合を発見しやすく、修理や調整もスムーズに行えます。
3.不具合が見つかった場合
定期点検で「動作不良」などの指摘があった場合は、速やかに修理・調整を実施してください。
火災時に正常作動しない防火シャッターは“設置していないも同然”になってしまいます。
関西エリアなら、「シャッター119」のように出張見積もりや修理を得意とする専門業者が多数ありますので、早めに依頼し安全性を取り戻しましょう。
なぜ点検が重要?~火災時の安全と法令順守
ここまで、防火シャッターの点検義務や罰則を中心に解説してきましたが、最後にもう一度点検の重要性についてまとめます。
- 人命を守る
火災発生時、シャッターが確実に閉まることで煙や炎の拡大を防ぎ、避難経路確保や被害最小化につながります。
もし動かずに炎が広がってしまえば、多数の死傷者を出す可能性も否定できません。 - 財産・事業を守る
工場や店舗などでは製品や機材を火災から守ることが事業継続に直結します。
防火シャッターが正常に作動すれば、延焼を防いで被害範囲を限定し、復旧コストを抑えられるでしょう。 - 法令を守る
定期点検と報告は建築基準法で明確に義務付けられ、罰則も存在します。
違反すれば信用失墜だけでなく、行政処分や経済的損失を被る可能性が高いです。 - 安心・信頼を得る
きちんと法定点検を行い、「防火設備が機能する建物」であると示すことは、テナントや利用者に対する安心材料にもなります。
徹底した防災対策は企業イメージの向上にも寄与します。
関西での防火シャッター点検・修理は「シャッター119」にご相談を
「法令で定められているなら、すぐに対応したいけれど、どこへ依頼すればいいの?」
そんな方は、ぜひシャッター119にお問い合わせください。
- 関西エリア(大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀)を中心に、店舗や工場、倉庫など大型シャッターの点検・修理実績が豊富です。
- 防火設備検査員や建築士との連携により、法定点検から修理・報告書作成までワンストップでサポートが可能。
- 無料相談・出張見積もりも承っておりますので、初めての方でも安心してご相談いただけます。
「うちは防火シャッターの数が多いんだけど、費用はどれくらい?」など、具体的な疑問があればお気軽に声をおかけください。
状況に合わせた最適なプランを提案し、法定点検をスムーズにクリアできるようお手伝いします。

まとめ:定期点検で“動く”防火シャッターを維持しましょう
防火シャッターは、ただ設置しているだけでは安全を守れません。
年1回の法定点検を行い、確実に作動する状態をキープすることが大前提です。
- 建築基準法で防火設備の点検・報告が義務化
- 対象は不特定多数の人が利用する建物など(特定建築物)
- 点検は有資格者しか行えず、年1回程度の報告が必要
- 怠れば100万円以下の罰金など厳しい罰則も
- 火災時に確実に作動しなければ意味がない
関西エリアで防火シャッターの点検や修理を検討されている方は、ぜひ「シャッター119」にご相談ください。
法律をクリアし、いざという時に人命や財産を守るためにも、“動く”防火シャッターを維持し続けることが何より大切です。
無料相談・出張見積もりの詳細は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
【ご依頼の流れ】
- 点検:まず、シャッターの損傷箇所を点検します。
- 見積もり:修理にかかる費用を見積もります。
- 修理:必要な部品を交換し、シャッターを修理します。
- 動作確認:修理後、シャッターが正常に動作するか確認します。
修理は、必ず依頼いただいたお客様とお話し、ご納得いただいた上で開始させていただきます。
「当初の見積もりよりも部品の発注をしないといけなくなりそう」「費用がかかりそう」だと判断した場合は、必ず手を止めて再度ご提案をさせていただきます。
いきなり修理を始めて、修理後にビックリする金額を請求するようなことはございませんのでご安心ください。

この記事の著者

シャッター119 編集部
シャッターに関するお役立ち情報を発信しています。代表の私が長年の経験に基づき、修理費用の目安、業者選びのポイント、日々のメンテナンス方法などを簡潔に解説。シャッターに関する疑問を、スピーディーに解決します。シャッターの修理・交換も「シャッター119」にお気軽にご相談ください♪