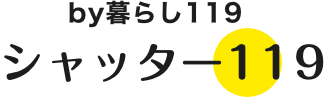緊急時でも安心!シャッターの台風対策方法と復旧フローを徹底解説
修理・交換2025.09.2
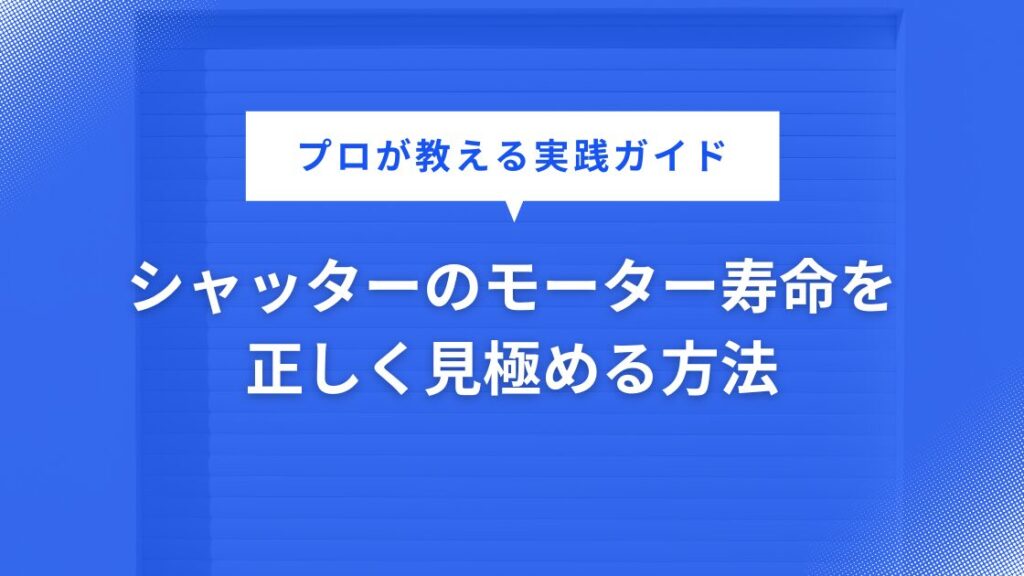
毎年のように勢力を増す台風。
シャッターは「最後の壁」ですが、正しい対策をしていないと“風で煽られてたわむ”“飛来物でスラットが歪む”“停電で閉められない”“冠水でモーターが故障する”など、営業・保管・防犯のすべてに直撃します。
しかも被害の多くは、台風が来る前の10分点検と当日のNG行為を避けるだけで高確率に回避できます。
本コラムではシャッターの台風に対する対策方法について、時系列のやることリスト、機種別の注意点、現場でできる強化策、プロが施す耐風アップグレードまで、関西の気象・地形特性を踏まえて実務的にまとめました。
最後に困ったときのために、プロへの無料相談・出張見積もりのご案内もご用意しました。
ぜひこのコラムをブックマークして、台風前後の実践マニュアルとしてお役立てください。
台風とシャッターのリスクを正しく理解する(基礎編)
台風時のシャッター被害は「風圧」「飛来物」「浸水」「停電・電装故障」の四重奏でやってきます。
ここを誤解したまま対処すると、かえって破損を招くことも。
まずは何が起きるのかをコンパクトに整理しましょう。
- 風圧・吸い上げ(負圧):正面からの押しつけだけでなく、建物周りの渦で吸い出し力が働き、スラットの端部・中段がたわみやすくなります。
- 飛来物衝突:看板・瓦・枝・資材などが点で衝撃を与え、レール噛み・スラット曲がりの起点に。
- 浸水・冠水:ボトムバーやガイドレール下端から水が侵入すると、錆・軸受け劣化、モーター・制御盤の絶縁低下を招きます。
- 停電・瞬低:電動シャッターは手動切替や非常開放の準備ができていないと、閉じられない/開けられない事態に。
ポイント:台風対策は「風圧に負けない固定」と「水・電気への備え」の二本柱です。
時系列でわかる:台風前48h~当日の対策チェックリスト
「いつ、何を、どの順でやるか?」は大切な現場スキル。
以下は標準作業手順としてそのまま使える時系列チェックリストです。
時間がなくても、★印だけは必ず実施を。
1. 48~24時間前(情報収集と準備段階)
- ★ 予報確認:暴風域通過の目安時刻・風向・最大瞬間風速を確認。
- ★ 人員と鍵管理:責任者・合鍵・非常時連絡網を再確認。
- 非常用手動操作の復習:電動は手動切替レバー/チェーンの位置と操作を確認(実際に1回だけ動作テスト)。
- 資材準備:養生テープ(低残留タイプ)、養生シート、布ガムテ、段ボール、ウエス、ケーブルタイ、シリコンスプレー、懐中電灯、絶縁手袋、ブルーシート、土のう・簡易止水板。
2. 24~12時間前(外構・開口部の軽整備)
- ★ レール・開口まわり清掃:砂・小石・落葉を除去。異物噛み込み=破損の引き金です。
- ★ スラット・下端ゴムの点検:裂け・欠落があれば簡易補修(仮で可)。雨水の侵入・たまりを防ぐ。
- 緩みチェック:ガイドレール固定ビス、ブラケット、巻取箱目地。目視で明らかなガタがあれば使用中止→プロ手配。
- 付帯物の撤去:のぼり旗、置き看板、プランター、自販機・灰皿の上物など風で動く物は屋内退避。
3. 12~6時間前(固定力を高める・飛来物対策)
- ★ 完全閉鎖&施錠:中途半端な開度(半開)は最悪です。全閉+鍵が基本。
- ★ 幅木ロック/落としの確認(手動)/ブレーキ状態(電動)をチェック。
- 内側養生:飛来物の二次被害を防ぐ目的で、内側から段ボール+養生シートを点在させて貼る(全面ベタ貼りは結露水溜まりの原因になるため避ける)。
- タイマー停止:自動開閉タイマーはOFFに。不要作動を防止。
4. T-6時間前~接近中(安全最優先)
- ★ 操作禁止:強風下の開閉は絶対にしない。無理な開閉はガイド外れ・スラット座屈の大半を占めます。
- 停電対応:停電したら無通電のまま。復電直後の誤動作・逆転があり得ます。
- 浸水警戒:入口前が冠水する地域は簡易止水板+土のうでバックウォーターを抑制。排水溝のゴミは直前にも再確認。
種類別・機構別の対策ポイント(手動/電動/オーバースライド)
シャッターは駆動方式や形状で弱点と手当てが変わります。
ここでは実務で差が出る要点だけを、要領よく押さえます。
1. 電動シャッター
- 手動切替/非常開放の位置と手順を、事前に写真付きで掲示。停電時の一回操作テストを推奨(人員・安全確保の上で)。
- 操作盤・受信部の防滴:庇がない場合は防滴カバーや簡易養生を。感電防止のため濡れた手で操作しない。
- タイマー・連動機器:台風モード(無効化)を準備。火災連動・非常放出は無効化しない。
- UPS・非常電源:導入済み現場はバッテリ健全性と自動復帰設定を確認。
2. 手動巻き取りシャッター
- 幅木ロック/スライドロックのかかり代を確認。摩耗で浅い場合は使用中止→点検。
- スプリング張力の過不足は風下側の座屈を招きやすい。違和感があれば操作を中止。
- 南京錠の位置:下端付近にぶら下げると振動でスラット損傷を誘発。専用位置に。
3. オーバースライドドア(上吊りパネルタイプ)
- トラック・ローラーの摩耗/ボルト緩みで風下側からの開きが起きやすい。事前の増し締めとレール清掃は必須。
- 手動開放時は強風下では絶対に行わない。パネルが風をはらむと回避不能。
「やってはいけない」台風時のNG行為
善意の応急措置が、実は破損の主因だったということもよくあります。
ここでは、よくあるNGを先に共有します。
一つでも心当たりがあれば、今日からやめてください。
- 半開で固定:風の出入りで共振→座屈。全閉+施錠が鉄則。
- 外側から全面ガムテ貼り:糊残り・塗膜傷み・水の逃げ道塞ぎで内部結露。貼るなら内側に点在。
- ブロックや物で下端を“抑える”:局所荷重でスラット変形。
- 安全装置(光電・エッジ)無効化:重大事故・法令違反。
- 強風下での開閉“試し”:最も多い破損原因。試すなら台風前に。
- スプレー油の過剰塗布:埃抱き込み→レール抵抗増。潤滑はシリコン系を薄く。
現場でできる“耐風・耐水”のちょい足し強化
大規模な改修をしなくても、いまからできる小さな工夫で耐風・耐水は底上げできます。
道具はホームセンターで揃う範囲です。
- レール内の砂止め:清掃後に薄くシリコンスプレー。油性はNG。
- ボトムゴムの簡易補修:隙間はEPDMゴム+両面ブチルで仮埋め(後日正式交換)。
- 開口内側の飛来物防護:段ボール+養生シートを点在。室内資材を1m以上退避。
- 排水の確保:前面の縁石・段差で水溜りができる場合は、簡易スロープ・止水板を“必要最小限”で。
- 操作手順の見える化:手動切替の写真・QR動画を貼り出す(平常時に撮影)。
プロが施す本格対策(耐風アップグレード&事前メンテ)
被害・停止の「確率」を本気で下げたいなら、構造側の底上げが効きます。
以下は現場条件に合わせて組み合わせるメニュー例。
費用はサイズ・仕様で変動するため、現地無料見積もりで最適化します。
- 耐風ガイドレール化:レール断面を強化し、抜け・座屈を抑える。
- ウインドロック/エンドロック:スラット端部の抜け止めを追加・強化。
- 中柱(センターポール)の設置:ワイド開口のたわみを大幅低減。
- ボトムバー補強/下端シール:風雨の入りと水押しを抑える。
- 巻取箱・ブラケット補強:箱のバタつき・振動対策。
- 防錆・耐塩害仕上げ:沿岸部は塗装/金物の仕様を変更。
- 制御盤の防滴・高所移設:冠水リスクを回避。
- 非常電源(UPS)・自動復帰設定:停電→復電の安全性・確実性を高める。
- 定期メンテ契約:バネ・レール・電装の年次点検で平常時の可用性を底上げ。
目安:軽度の強化は数万円台~、構造強化は十数万~数十万円。台風一回の停止損失を考えれば、投資対効果は高い現場が少なくありません。
台風前10分で終わる「プロ直伝・最終点検」テンプレ
忙しくてもこの10項目だけは実践してみてください。
A4に印刷して現場に掲示すれば、誰がやっても同じ品質で点検できます。
- 全閉&施錠(半開禁止)
- レール内の異物除去(砂・小石・落葉)
- スラットの歪み・傷の目視
- 下端ゴム・側シールの欠損有無
- ロック/ブレーキの確実なかかり
- 操作盤・受信部の防滴養生
- 手動切替の位置・手順を再確認
- 自動タイマー停止(誤作動防止)
- 前面の飛散物撤去(看板・のぼり)
- 緊急連絡網・合鍵の最終確認
台風通過後の“やること”リスト(復旧・点検・記録)
通過直後は焦りがち。
ですが、順番とやってはいけないことを守ると、二次被害を防げます。
保険・賠償の観点でも記録は重要です。
- 通電前に外観確認:スラット波打ち・レール外れ・箱の傾きがあれば通電禁止。
- 冠水・浸水の確認:操作盤・モーターに水跡があれば絶対に通電しない。
- 写真記録:全体・近接・銘板・室内側・外構を時系列で撮影。
- 手動で“わずかに”動かす:抵抗・異音があれば即停止。無理はしない。
- 清掃→乾燥→点検の順で。湿気が残る状態での通電はNG。
- 保険相談:風災・水災が想定される場合は早めに連絡。見積・報告書は業者発行で。
関西エリア特有の留意点(地形・気象の“クセ”)
同じ台風でも、関西のどこにいるかで被害パターンが変わります。
日頃の対策メニューは地域仕様に寄せるのがコツ。
- 大阪湾沿岸(大阪市・堺市・尼崎市など):塩害+突風。防錆・端子腐食対策、レール清掃の短サイクル化を。
- 紀伊半島沿岸(和歌山市・海南市):南寄り強風と吹き返し。ボトム・側シールの強化が効く。
- 京都・奈良の内陸盆地:風は弱めでも豪雨が長引く。止水・冠水対策を重視。
- 滋賀(琵琶湖周辺):吹き出し風+長雨。排水・結露のケアと絶縁点検を。
事例ミニケース(対策→効果のイメージ)
「うちにも効く?」の声に、よくある三例を要点だけ共有します。
現場条件により結果は異なりますが、検討のヒントになるはずです。
- ケースA:幅5.5m 店舗軽量シャッター
対策:中柱新設+耐風レール+ボトム補強。
結果:強風時のたわみ量が体感1/3に。飛来物痕は残るも噛み込みなし。 - ケースB:倉庫電動(湾岸沿い)
対策:制御盤高所移設+防滴+UPS。
結果:停電→復電後の誤作動ゼロ、冠水でも電装健全。 - ケースC:内陸ガレージ群
対策:年次メンテ契約(台風前後点検含む)。
結果:開かない故障ゼロ、小修繕を早期実施でトータル費用削減。
よくある質問(Q&A)
台風前後に寄せられる質問をQ&Aで簡潔にまとめました。
迷ったら操作を止めてシャッター119にご相談ください。
Q1. 半開で風を“逃がした方が良い”って本当?
A. 誤りです。風の出入りで共振し、座屈・抜けの主因になります。全閉+施錠が原則。
Q2. テープを外側にベタ貼りして補強は?
A. 推奨しません。糊残り・塗膜劣化・水の逃げ道封鎖で逆効果。貼るなら内側に点在で飛散抑制目的に。
Q3. 台風中に閉め忘れに気づいたら?
A. 操作しないでください。強風下の開閉は最も壊れやすい瞬間。安全確保を優先。
Q4. 冠水後、乾いたら電源を入れて良い?
A. NG。内部絶縁が低下している恐れ。専門点検→乾燥→絶縁測定が先です。
Q5. どの潤滑剤が良い?
A. シリコン系を薄く。油性でベタつくスプレーは埃抱き込み→抵抗増で逆効果。
Q6. 台風前の“最低限”は?
A. 全閉施錠・レール清掃・タイマーOFF・手動切替確認。この4点で大半の事故を回避。
Q7. 風で箱(シャッターボックス)がバタつく
A. 固定金具の緩み・箱板金の変形の可能性。使用中止→点検が安全です。
Q8. 自動ドア連動や警備連動はどうする?
A. 台風モードの有無を確認。必要に応じてシャッター側を優先ロジックに。安全装置は無効化しないこと。
Q9. 保険は使える?
A. 風災・水災が対象のことがあります。被害状況の写真と業者報告書を早めに準備。
Q10. 予算に限りがある。どこから強化?
A. ①全閉の確実化(ロック) ②レール清掃と下端シール ③中柱 or 耐風レールの順がおすすめ。
まとめ
台風対策は難しくありません。
予報を見て準備し、シャッターを正しく“固定”し、電気と水をコントロールすれば、被害確率は大きく下がります。
最後に要点だけ再掲します。
- 半開禁止。全閉+施錠が大原則。
- レール清掃・下端シールで噛み込みと浸水を予防。
- 強風下の開閉はしない。停電時は手動切替に備える。
- 外側ベタ貼り養生は逆効果。やるなら内側に点在。
- 本気で止めたいなら耐風レール・中柱・端部ロックなどの構造強化を。
- 通過後は通電前に外観確認→記録→点検。無理は禁物。
台風対策の8割は準備で決まります。
ぜひこれを肝に命じておいていただければと思います。
なお、台風前後の安全点検・応急復旧・耐風アップグレードなどのご要望があれば、お気軽にシャッター119にお問い合わせください。
関西全域(大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀)で、ご相談・お見積もりは無料です。
緊急時も日程を柔軟に調整し、事業停止の時間を最小化します。
【ご依頼の流れ】
- 点検:まず、シャッターの損傷箇所を点検します。
- 見積もり:修理にかかる費用を見積もります。
- 修理:必要な部品を交換し、シャッターを修理します。
- 動作確認:修理後、シャッターが正常に動作するか確認します。
修理は、必ず依頼いただいたお客様とお話し、ご納得いただいた上で開始させていただきます。
「当初の見積もりよりも部品の発注をしないといけなくなりそう」「費用がかかりそう」だと判断した場合は、必ず手を止めて再度ご提案をさせていただきます。
いきなり修理を始めて、修理後にビックリする金額を請求するようなことはございませんのでご安心ください。

この記事の著者

シャッター119 編集部
シャッターに関するお役立ち情報を発信しています。代表の私が長年の経験に基づき、修理費用の目安、業者選びのポイント、日々のメンテナンス方法などを簡潔に解説。シャッターに関する疑問を、スピーディーに解決します。シャッターの修理・交換も「シャッター119」にお気軽にご相談ください♪