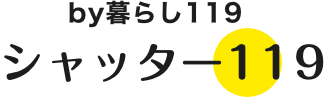【緊急・保存版】シャッターが勝手に開く原因と止め方・再発防止のすべて
修理・交換2025.10.21
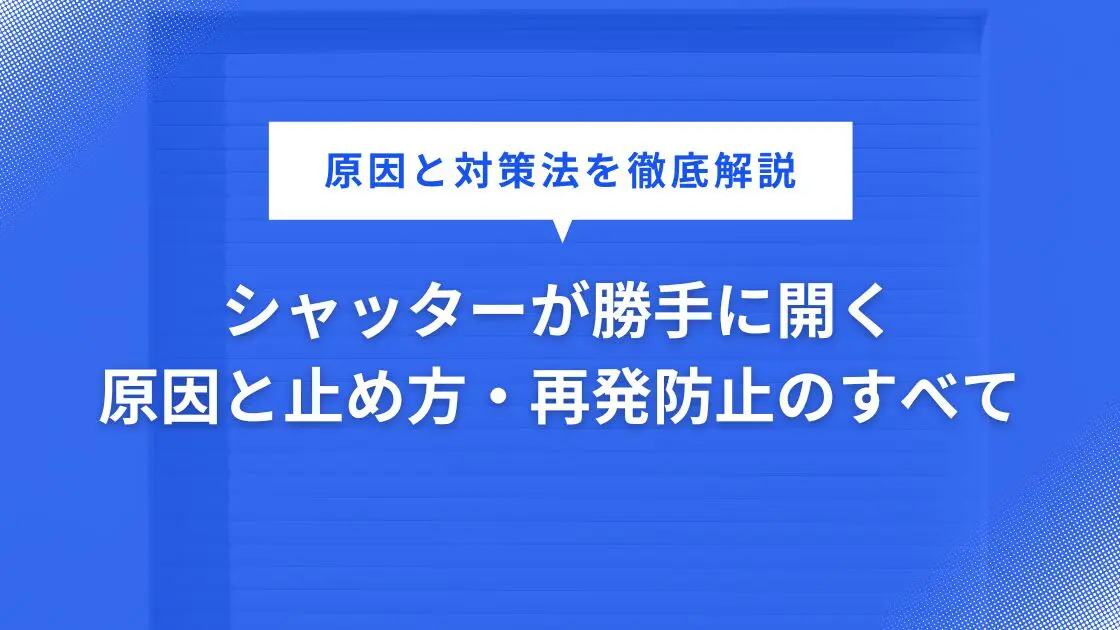
最初にお伝えしたいのは、「勝手に開く」は偶発ではなく“兆候の結果”という事実です。
閉店後の無人時間帯に半開き、夜間の強風時に突然上昇、朝に出社したら全開で止まっていた。
こうした事例は、誤信号(リモコン・受信機・上位システム)、安全装置の反転動作、電磁ブレーキ不良、タイマーやBAS(ビル管理システム)の設定ミス、強風・室内負圧・落雷サージといった要因のどれか一つ、あるいは複数の重なりで起こります。
そして、対応の優先順位は明確です。①止める(二次動作の抑制と仮固定)、②見極める(安全に配慮した切り分け)、③守る(根因対処と運用の仕組み化)。
この順を踏めば、その日のうちに安全度を回復できるケースが多いのです。
本コラムでは、現場でそのまま使える初動手順と高精度の切り分け、原因別の恒久対策と費用感、さらに組織として再発を防ぐ運用設計まで、わかりやすくまとめました。
初動フローの「理由」と「コツ」
突然の上昇や半開状態を前に、焦って操作を繰り返すのは最悪手です。
人身事故・二次故障・証拠の消失を防ぐため、最初の3分でやるべきことを、なぜそれが必要なのかという理由とともに解説します。
STEP0|危険域の排除(30秒)
シャッターの可動範囲は危険域です。まずはパイロンや養生テープで立入禁止を作り、通行人・台車・車両の動線をいったん止めます。事故は「想定外の再動作」時に起きます。動線遮断は二次事故の抑制につながります。
STEP1|勝手動作を止める(60秒)
電動なら操作盤の非常停止→シャッター専用ブレーカーOFFへ。これで制御の誤動作や混信による再起動を遮断できます。手動なら幅木ロック・内落し棒などの機械的固定を。走行部を紐で縛る行為は巻き込み・破断の危険があるため避けてください。
STEP2|施錠・仮固定(60〜120秒)
錠前が機能するなら施錠、機能しない・鍵が見当たらない場合は養生バンド等で下端を躯体の金物に仮固定。ポイントは「走行部に触れず、可動干渉しない箇所に固定する」ことです。強風時は上下の振れ止めも有効ですが、詰め物をガイドへ押し込むのは噛み込みの原因になるためNG。
STEP3|記録(120秒)
「何が、いつ、どれくらい」の証拠を残すと、その後の復旧速度が段違いに速くなります。時刻・開き量・回数・天候や設備変更をメモし、全景・操作盤・受信機・センサーの写真と10〜20秒動画を撮影。ここで再通電テストはしないでください。原因不明のまま再現すると、想定外の再起動=二次事故のリスクがあります。
ここまでで、安全と証拠が確保できました。
次は、再通電せず“見て・考える”切り分けです。
「勝手に開く」の全体像
原因をA:制御・信号/B:安全装置・設定/C:駆動・機械/D:環境の4領域に分けて眺めると、切り分けの順路が明瞭になります。
最終的には複合要因も多いのですが、第一仮説を立てるだけでも復旧の道筋が短くなります。
- A|制御・信号:リモコン(押下・液漏れ)/受信機の混信/タイマー・BAS(ビル管理)・警備・火報の連動/配線端子の結露・腐食・サージ
- B|安全装置・設定:光電センサー遮光・汚れ→反転再上昇/セーフティエッジ断線/リミット(上下限)ズレ/非常開放の電動復帰忘れ
- C|駆動・機械:電磁ブレーキ保持不良→停止後じわ上昇/手動機のバネ張力・巻取り不平衡
- D|環境:強風・室内負圧(換気・厨房)・温度差結露・落雷サージ
例えば「閉店後、毎夜0:05頃に開く」ならAのタイマー・BAS、「雨後に閉まらず戻る」ならBのセンサー、「停止後じわじわ」ならCのブレーキ、「海風・強風日だけ」ならDの風圧・負圧が疑わしい、といった具合です。
3分で切り分け。再通電しないで、ここまで分かります
切り分けのポイントは「触らず、見て、隔離する」。
つまりリモコン・受信・設定・安全装置・機械保持の5視点で、再通電なしに仮説を立てます。
1. 操作系の隔離
まずは携帯リモコンを全回収し、電池を抜いて保管します。
押し跡やゴムの戻り不良、落下痕、液漏れがあれば、誤送信の元です。
壁スイッチはカバーで封印できればベター。
これで意図しない“外部入力”を遮断できます。
2. 受信機まわり
直近の設備更新(LED照明・無線AP・防犯周辺機器など)をヒアリング。
433/315MHz帯は電源ノイズ(LED電源・インバータ)や無線機器で感度が乱れます。
受信機のアンテナ延長や移設痕跡があれば、そこで混信・感度異常が起きている可能性があります。
3. タイマー・BAS・警備/火報
開放スケジュールやBAS連動のインターロックは便利な反面、設定ミスが少なくありません。
「誰が・いつ・どの画面で」変更したのか、直近の論理更新履歴を確認しましょう。
変更者の特定は、再発防止に効きます。
4. 安全装置・設定
光電センサーのレンズや反射板の汚れ・曇り・傾きは、反転再上昇の主要因。
セーフティエッジの断線やケーブル切れも引き金です。
非常開放レバーが電動復帰の位置にあるかも確認。
ここが戻っていないと、反力や風圧で「じわ上がり」が発生します。
5. 機械保持(ブレーキ)
下端を軽く押す・上げることで、保持力の手応えを探ります(落下・巻込みに注意)。
停止後すぐに数センチ上昇する、明らかに軽い/重いなどがあれば、電磁ブレーキや手動バネの不良が疑われます。
ここはDIY禁止領域です。
この5視点で「どの領域が濃厚か」が見えます。
ここまでの所見(メモ・写真・動画)をもってシャッター119へご連絡いただければ、初回訪問で終わらせられる確率が大きく上がります。

やってはいけないこととは?
- 再通電の連打:偶発要因が残っていれば再現→事故。基板やブレーキの熱ストレスも増やします。
- 安全装置の短絡・無効化:法令・保険・安全のすべてでNG。もし事故が起きれば重大責任を負います。
- 制御盤の分解・接点復活剤:感電・火災リスクに加え、接点劣化を促進。
- バネ張力の自己調整:強大なエネルギーを持つ部位。作業誤りは重傷事故につながります。
- 人・車両の下で試運転:予期しない再動作の際に直撃します。可動範囲外から確認しましょう。
原因別に“なぜ起こり、どう直し、どう防ぐか”を丁寧に
A|制御・信号の問題(リモコン/受信機/タイマー・BAS)
リモコン誤作動は、ボタンの戻り不良・液漏れ・落下変形が典型です。
全回収→電池抜きで一時隔離し、怪しい個体は廃棄が安全。プロはIDの整理・再発行、同番(同一ID)の最適化やキーロック付きへの移行を提案します。
受信機の混信は、LED照明や無線AP更新が引金になりがち。受信機の移設・アース強化・アンテナ指向性調整、必要ならフィルタリングや有線優先化で実害を断ちます。
タイマー・BAS・警備/火報連動は、「便利さ」の裏に設定ミスのリスク。インターロックを論理から点検し、権限者を限定。
変更履歴の台帳化を運用に組み込むと、再発を確実に防げます。
シャッター119の強み①|電気×システム
現場では、シャッター本体だけでなく受信機・BAS・警備連動の調整が必要になるケースが多数あります。当社は電気工事士×機械整備の混成チームで、論理(設定)から物理(配線・機器)までワンストップ。訪問回数・調整工数を最小化します。
B|安全装置・設定の問題(光電・エッジ・リミット・非常開放)
光電センサーは黄砂・雨滴・結露・反射板の傾きで誤検知します。
清掃で収まらない場合は光軸合わせ・感度調整、断線時は交換が必要です。
リミットのズレは、巻取りの径変化・衝撃などを契機に起きます。
再設定はプロ作業。誤った再設定は落下・巻込みのリスクがあります。
非常開放→電動復帰忘れは、停電・点検後に起きがち。
レバー位置の写真入り手順書を盤扉に貼り、ダブルチェックを習慣化しましょう。
シャッター119の強み②|安全を損なわない現場復旧
センサー・リミット・非常開放は、「動くようにする」より「安全に戻す」が先。私たちは安全装置を活かした復旧を標準化。写真付き報告書で、どこに何を施したか、監査や保険にも使える形でお渡しします。
C|駆動・機械の問題(電磁ブレーキ・バネ・巻取り)
電磁ブレーキの摩耗・調整不良は最優先で整備すべき領域です。
停止保持が甘くなると、停止後じわ上昇が発生し、防犯面・安全面で致命的。
分解整備・交換とともに、巻取り・軸受の負荷診断を行い、必要に応じてモーターASSYで更新します。
手動機のバネは、張力過多・左右不平衡で自走や片上がりを誘発します。
ここは高エネルギー部位につきDIY厳禁。再調整・交換は経験と専用治具が不可欠です。
シャッター119の強み③|重整備を短時間で
ブレーキ・バネ・巻取りといった重整備を、高所作業・時間外でも迅速に。在庫前積みと複数台同日の段取りで、ダウンタイムと総額を抑えます。
D|環境の問題(強風・負圧・結露・サージ)
強風・室内負圧は、サイドや下端のシール劣化と重なると吸い上げ・風切り音・再上昇を誘発します。サイド/ボトムシール更新・補助ロックで対処し、厨房や大型換気がある現場は給気計画(通風スラット等)で圧バランスを正すのが本命です。
落雷サージは、基板フリーズや誤動作を引き起こします。
SPD(サージ保護)や盤内の防滴・結露対策、気象注意報時の運用で予防しましょう。
シャッター119の強み④|立地・季節対応
関西は黄砂→梅雨→台風の三段階でリスクが変化。沿岸(大阪湾・和歌山)/幹線沿い(粉塵)/内陸盆地(結露)の地域特性に合わせたメニューをご提案します。

費用相場と工期の目安(関西エリア)
丁寧な診断のうえでの目安ですが、意思決定の参考に価格レンジをお伝えします。
ただし、サイズ・高さ・時間帯などで上下しますので、必ず現地調査のうえ最終価格はご確認ください。
- センサー清掃・軸合わせ・感度調整:15,000~40,000円/60~90分
- 受信機調整・有線優先化(軽改造):20,000~60,000円/90~120分
- リミット再設定:20,000~50,000円/60~90分
- ブレーキ整備・交換:40,000~120,000円/90~180分(機種依存)
- タイマー・BAS論理是正:要見積(システム構成による)
- サイド/ボトムシール更新・補助ロック:6,000~40,000円/枠/30~120分
早期連絡=軽作業で完結のチャンス。「閉め直して様子見」は再発の温床です。
止める→隔離→記録→相談が最短です。
「仕組み」で二度と起こさないための運用・点検・教育
「勝手に開く」をゼロにするには、一度直すだけでなく、仕組みで防ぐことが大切です。
今日から始められる実務的な4ステップを提案します。
1. SOP(標準手順)の掲示
非常停止→専用ブレーカーOFF→施錠・仮固定→記録→連絡先を写真付きで盤扉に貼付。非常開放→電動復帰の手順も写真で。誰が見ても同じ品質で初動できるようにします。
2. 月次ミニ点検(10分/台)
センサー・反射板の清掃、レールの掃除機+乾拭き、外装の軽い増し締め、短ストローク試験。写真と所見を残し、前回記録と比較します。
3. 変更履歴の台帳化
タイマー・BAS・受信機位置・アンテナ・ID再登録の履歴を一元管理。「誰が・いつ・何を・なぜ」を残すと、原因追跡と監査対応が格段に楽になります。
4. 季節前の先回り巡回
黄砂・梅雨・台風・落雷に合わせて臨時点検。脆弱部(センサー・外装・盤)を重点ケアします。
シャッター119の強み⑤|運用も一緒に作る
作業して終わりではありません。SOPテンプレート・点検台帳テンプレを無償提供し、再発防止の仕組みまで伴走します。

関西の改善事例を公開します
- 大阪市港区/ロードサイド店(電動1枠)
症状:閉店後、毎夜半開。LED照明更新後から。
原因:受信機の混信(照明ノイズ)。
対策:受信機移設+アンテナ調整、有線優先化。
結果:再発ゼロ。37,400円/90分。 - 神戸市中央区/倉庫(電動4枠)
症状:雨後に反転→再上昇。
原因:光電センサー汚れ・軸ズレ。
対策:清掃・軸合わせ・感度調整。
結果:安定稼働。14,300円/枠。 - 堺市西区/駐車場(電動1枠)
症状:停止後にじわ上昇。
原因:電磁ブレーキ摩耗。
対策:ブレーキ交換・駆動負荷点検。
結果:保持良好。71,500円。 - 京都市伏見区/工場(電動・BAS連動)
症状:夜間スケジュールで勝手に開放。
原因:BAS論理の更新ミス。
対策:スケジュール修正・権限者限定・台帳化。
結果:再発なし(システム側は個別見積)。
よくある質問(FAQ)
Q1. 閉め直したら収まりました。様子見でいいですか?
A. おすすめしません。原因が残っていれば再発します。まずは停止・施錠・隔離、次に切り分け→根因対処へ。
Q2. 受信機の電源を抜けば安全ですか?
A. 一時的な隔離としては有効ですが、有線系・設定要因が残る可能性があります。診断→恒久対策が必要です。
Q3. 防火シャッターですが同対応でOK?
A. 不可。防火設備は認定構造と法令が関わります。安易な改造は禁止。所管の定期点検も忘れずに。
Q4. 夜間・早朝でも来てもらえますか?
A. 可能です。関西全域で時間外枠をご用意。症状の写真・動画を事前共有いただくと、当日中の概算→最短訪問ができます。
Q5. 費用が不安です。
A. 現地診断・見積は無料。現場で最小コスト案/再発防止案/段階導入案を並べ、意思決定を支援します。
まとめ
それでは最後に、リスクをゼロに近づけるためのステップ(止める→見極める→守る)についてまとめさせていただこうと思います。
- 止める:非常停止→専用ブレーカーOFF→施錠・仮固定→記録。
- 見極める:リモコン隔離/受信・設定履歴/安全装置・機械保持。再通電はしない。
- 守る:受信・設定・安全装置・ブレーキなど根因ごとの恒久対策。
- 運用:SOP掲示・月次点検・変更履歴台帳・季節前巡回で仕組み化。
シャッターが勝手に開くのは偶然ではありません。
小さな調整と正しい段取りで、今日からリスクを限りなくゼロへ減らすことを目標にしてみてください。
なお、シャッターのことで少しでも疑問やお困りのことがあれば、シャッター119にお気軽にご相談ください。
関西の現場を止めないために、安全・防犯・コストを同時に守る最短ルートを、シャッター119が責任をもってご提案します。
【ご依頼の流れ】
- 点検:まず、シャッターの損傷箇所を点検します。
- 見積もり:修理にかかる費用を見積もります。
- 修理:必要な部品を交換し、シャッターを修理します。
- 動作確認:修理後、シャッターが正常に動作するか確認します。
修理は、必ず依頼いただいたお客様とお話し、ご納得いただいた上で開始させていただきます。
「当初の見積もりよりも部品の発注をしないといけなくなりそう」「費用がかかりそう」だと判断した場合は、必ず手を止めて再度ご提案をさせていただきます。
いきなり修理を始めて、修理後にビックリする金額を請求するようなことはございませんのでご安心ください。

この記事の著者

シャッター119 編集部
シャッターに関するお役立ち情報を発信しています。代表の私が長年の経験に基づき、修理費用の目安、業者選びのポイント、日々のメンテナンス方法などを簡潔に解説。シャッターに関する疑問を、スピーディーに解決します。シャッターの修理・交換も「シャッター119」にお気軽にご相談ください♪