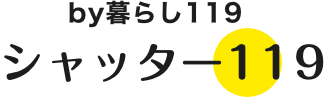シャッターのメンテナンス点検項目・完全ガイド(現場でそのまま使えるチェックリスト付き)
修理・交換2025.09.27
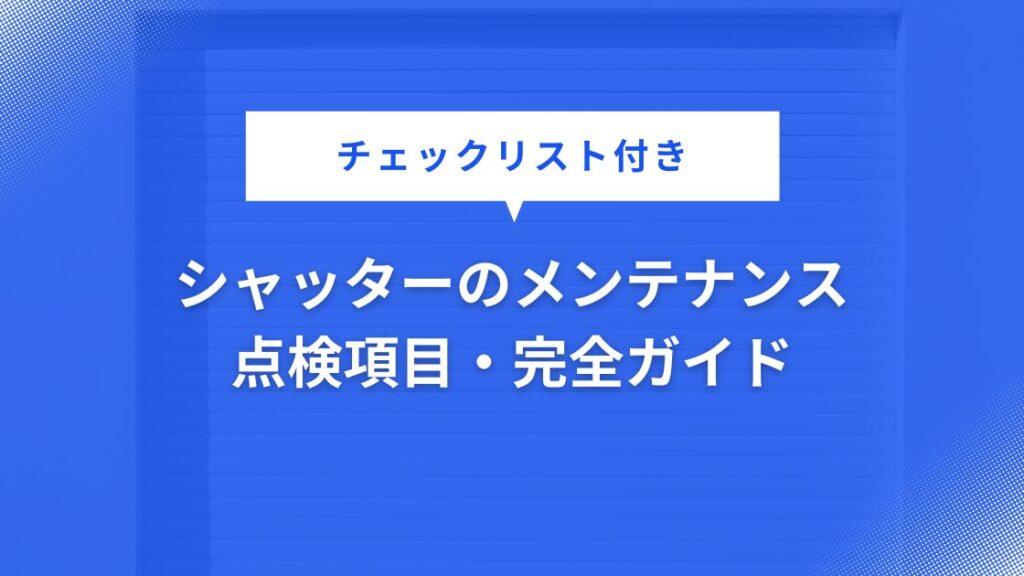
「毎日の開閉はできているけれど、本当に安全な状態か自信がない」「音や動きが“なんとなく”怪しいが、どこを点検すれば良いか分からない」「点検記録を残すように言われたが、項目がまとまっていない」
関西(大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀)で頂くご相談の多くは、“点検の型がない”ことによる見落としに起因します。
シャッターは重量物で可動部が多い設備です。
点検の勘所を外すと、突発停止・巻上げ不能・落下事故のリスクが上がり、結果的に修理コストも膨らみます。
逆に言えば、正しい点検項目を“決め打ち”で回すだけで、故障の多くは未然に防げます。
本コラムは、現場でそのまま使える「シャッターのメンテナンス点検項目」を、頻度別・種類別に整理した保存版です。
後半には印刷して運用できるチェックシートと、異常の判定基準/プロに任せる境界線も掲載。
無料相談・出張見積もりのご案内もございますので、迷ったらいつでもお声がけください。
なぜ「点検項目」を固定化するのか(考え方と頻度設計)
点検は「見る」ではなく“決まった順番で確認し、記録して比較する”行為です。
項目の固定化と記録の蓄積があってはじめて、「前回との違い」「再発傾向」「交換の適期」が見えます。頻度は日常・月次・半期/年次の3段で設計し、現場の使用回数・環境(粉じん/塩害)で増減させましょう。
以下の基本設計をベースに、貴社の現場に合わせて調整してください。
- 日常(毎日/当番制):開閉テスト・異音・引っ掛かり・目視の安全確認
- 月次(設備担当):清掃・潤滑・固定部の増し締め・消耗の傾向チェック
- 半期/年次(専門点検):電装・バランス・巻取り機構・法定点検(該当設備)
ポイントは“いつもと違う”を数値と写真で残すこと。
経時変化が早期発見の決め手です。
点検前の安全準備と必要ツール(最重要)
点検で最優先すべきは作業者と周囲の安全です。
可動部への巻き込まれ、落下、感電…
不適切な手順は重大事故につながります。
以下の手順とツールを準備し、「できる範囲」と「触れない範囲」を明確にしましょう。
電気部・高所・重整備はプロへが鉄則です。
- 安全手順:動作確認以外の作業時は主電源OFF/鍵抜き→可動範囲に人がいないことを声掛け→施錠・表示
- 個人装備:手袋/保護メガネ/ヘルメット/反射ベスト(夜間)/脚立は転倒防止者を配置
- 基本ツール:懐中電灯、ブラシ/ウエス、掃除機、シリコン系潤滑剤、+/-ドライバー、六角、トルクレンチ(軽整備まで)
- NG:高所作業車・分解・バネ張力・電気配線→専門業者(有資格)へ
- 電動の注意:リモコン・制御は誤作動防止で電源OFF。活線部のカバー開放禁止。
手動シャッターのメンテナンス点検項目(基本)
手動シャッターは構造がシンプルな反面、レール摩耗・バネ劣化・スラット変形の影響を直に受けます。
以下は日常~月次で回す“外せない”項目です。
チェック形式で場内巡回の定型化にご活用ください。
日常(開閉時のその場チェック)
- □ 動作:引っ掛かり/途中停止なし、最後まで密閉・全開できる
- □ 音:「ギシギシ」「ガリガリ」などの異音なし(※聞こえた位置を記録)
- □ 姿勢:開閉中に左右どちらかが先行/遅延しない(傾き確認)
- □ 安全:手を放しても急落下しない、途中保持が効く(バネ補助の確認)
- □ 鍵/ロック:施錠・解錠がスムーズ、鍵穴の抵抗なし
月次(停止状態での近接点検)
- □ レール:溝の砂・小石・金属粉を除去、歪み・傷・錆の有無
- □ スラット:曲がり/端部の潰れ/連結ピン緩み、塗膜剥がれ
- □ 巻取り側(見える範囲):異常な偏摩耗・異音なし(ボックスは無理に開けない)
- □ 固定:ガイド・ブラケットのボルト緩み増し締め(届く範囲・規定外の分解は不可)
- □ 潤滑:シリコンスプレーをレール内面と可動接点に薄く(汚れを拭き取ってから)
- □ 下端ゴム:欠け・硬化・裂けの有無(雨水侵入・騒音源)
目安として、潤滑は半年~年1回でも可です。
ただし月次清掃→異音が出たら都度スポット潤滑が効きます。
電動シャッターのメンテナンス点検項目(電装追加)
電動は機械+電気+安全装置の複合体です。
日常は“使い勝手”で異常を拾い、月次は清掃・潤滑・固定を手動と同様に。
電源・配線・制御盤・センサーは目視範囲の異状有無の確認までに留め、内部は専門業者に委ねてください。
日常(操作時)
- □ 起動:リモコン/押し釦の反応遅延なし、押下と動作の同期
- □ 停止:所定位置で自動停止、反転・勝手停止がない
- □ 異音/振動:モーター唸り・周期的なガタつきの有無
- □ 安全装置:障害物があると停止/反転する(テストは安全配慮の上、年1回目安)
月次(停止状態で)
- □ 配線の目視:被覆の擦れ・挟み込み・焼け跡なし(内部開放は不可)
- □ 制御盤外観:表示ランプ/エラー表示の有無、結露・水滴跡なし
- □ 受信部/アンテナ:固定・位置ズレ・断線なし(清掃)
- □ チェーン/ベルト露出部:過度なたるみ・欠け・切れ毛なし(見える範囲)
- □ 潤滑・固定:レール・可動部の清掃と薄塗り、ボルト緩み軽整備
- □ 非常手動復帰:非常開放→電動復帰の操作手順を年1回確認(本番時の混乱防止)
注意点として、電気配線・制御盤内部・モーター交換は電気工事士の領域です。
異常の“兆候”を掴んだら早めにプロへご相談ください。
環境別/イベント別の追加点検(見落としがちな要注意ゾーン)
使用回数と環境は劣化の加速度を決めます。
粉じん・塩害・強風・豪雨/台風後は、定例に加えて臨時点検を。
特に関西沿岸部・幹線道路沿い・工場帯では、通常頻度より1.5~2倍の清掃・確認が目安です。
- 海沿い/塩害地:スラット下端・レール下部の白錆・膨れ、ねじ頭の腐食→真水洗浄+乾拭き
- 粉じん・切削粉:レール・下枠ゴム周りの金属粉堆積→掃除機+湿拭き→乾拭き
- 台風・暴風後:スラットの点変形・擦り傷、レールの捻じれ/異物噛み、固定の緩み
- 豪雨後:制御盤・受信部の浸水痕/結露、下枠ゴムの水切れ不良
- 冬期:凍結による張り付き→無理に駆動せず、氷解→清掃→薄潤滑
異常の判定基準(“様子見”と“即プロ”の境界線)
“違和感”を言語化し、行動基準に落とすと判断に迷いません。
以下は現場で多い症状を3段階に色分けした基準です。A=緊急/B=早期/C=経過観察と覚えてください。
- A:緊急(即停止→専門業者)
・急落下/保持不可 ・電源投入で焦げ臭い/発煙 ・レール外れ/スラット脱落の恐れ
・電動の勝手動作/反転の連発(安全装置・制御異常の疑い) - B:早期(当日~1週間以内にプロ相談)
・同一位置で毎回の引っ掛かり ・周期的なガタン音/振動 ・傾き/片寄り
・チェーン/ベルトの毛羽立ち・ひび ・レール歪み・錆隆起 - C:経過観察+自主管理
・軽いきしみ音(清掃・薄潤滑で改善) ・軽微な塗膜剥がれ(錆転防で抑制)
・鍵穴の渋り(清掃・少量潤滑)
迷ったら安全側(B以上)に倒してください。
人が下にいる状態での試運転は厳禁です。
そのまま使える!点検チェックリスト(日常/月次/半期・年次)
以下は印刷・転記して運用できる実務テンプレです。
点検者・日時・所見・写真IDを必ず残し、“同じカメラ位置”で撮るのが比較のコツ。
必要に応じて項目の追加・削除を行ってください。
★日常点検カード(10分でOK)
- 施設名:___ / シャッターID:___ / 点検者:___ / 日付:___
- □ 開閉良好 □ 引っ掛かり無 □ 異音無 □ 傾き無 □ ロックOK
- 所見メモ:________________ 写真ID:____
★月次点検票(30~40分/台)
- 清掃:レール溝・下枠・スラット表面(□ 実施/□ 未)
- 固定:ガイド・ブラケット・取付ビス増し締め(□ 問題無/□ 要是正)
- 潤滑:シリコン系を薄塗り(□ 実施)
- 電動のみ:配線目視/制御盤外観/受信部(□ 正常/□ 気づき有→所見へ)
- 所見・次回アクション:__________ 写真ID:____
★半期・年次点検(専門点検の指示書として活用)
- 依頼内容:巻取り機構・バランス・安全装置・電装の総合点検/整備提案
- 運用条件:日開閉回数__ 異常履歴__ 環境(塩害/粉じん/沿道)__
- 付帯:過去12か月の写真台帳・点検票コピー添付
よくある不具合とその原因、そしてまず行うこととは?
「症状→原因→最初の一手」を表でまとめました。
安易な分解は厳禁、まずは安全第一で切り分けましょう。
| 症状 | 想定原因 | まず行うこと(DIY範囲) | |
|---|---|---|---|
| 途中で重くなる/同位置で引っ掛かる | レール異物/歪み、スラット端部変形 | 清掃→薄潤滑→目視撮影 | レール修正/スラット端整形・交換 |
| ガタンガタンの周期音 | チェーン・ベルトたるみ/ローラー摩耗 | 目視・写真記録 | 張り調整/テンショナー整備/交換 |
| 電動が勝手に止まる・反転 | 障害物検知/センサー汚れ・ズレ/制御誤作動 | センサー清掃・位置目視 | センサー調整/制御診断・交換 |
| 急に重くなった(手動) | バネ張力低下/固定緩み | 使用中止・写真記録 | バネ調整・交換/ブラケット補強 |
| 異音+焦げ臭い(電動) | モーター・配線異常 | 即停止・通電禁止 | 電気診断・モーター/配線交換 |
DIYで“やってよいこと/いけないこと”の線引き
“自主管理でコスト最適化”には大賛成です。
ただし安全と法令に抵触する部分はプロに丸投げが正解です。
線引きの明確化が事故と二度手間の回避につながります。
- やってよい:清掃/外観点検/レールへのシリコン系薄潤滑/外側のビス増し締め/非常開放~電動復帰の手順確認
- やってはいけない:ボックス内部開放/バネ調整・交換/電源・配線作業/高所作業車を用いる作業/安全装置の無効化(危険)
防火シャッターの“法定”点検(対象の方は必読)
防火シャッター(防火設備)は建築基準法の定期報告制度に基づき、所定周期での検査・報告が求められます。
有資格者による検査・書式での報告が前提です。
対象か不明な場合は設置台数・場所・用途をご準備の上、まずはご相談ください。
- 運用:年1回を基本に、自治体・設備区分で周期が定まる場合あり
- 求められる記録:作動試験・閉鎖確認・障害物検知・復帰・不具合是正履歴
- 依頼先:防火設備の検査・報告に対応できる有資格者(※当社手配可)
店舗・複合施設・倉庫など対象用途のテナント入替時も要注意。
早めの計画が無駄な休業を防ぎます。
シャッター119の点検・メンテナンス(関西全域)
シャッター119では、関西全域(大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀)で、無料現地診断・出張見積りに対応。
日常点検の型づくり~年次点検・整備・法定点検手配まで、現場実務に即したサポートをワンストップでご提供します。
- 無料:現地診断・見積り、所見レポート(写真添付)
- 迅速:緊急トラブルは一次復旧を最優先(スケジュールにより最短即日)
- 品質:電動は電気工事士チーム、必要に応じて有資格検査員と連携
- 運用:チェックリストのカスタム作成・点検台帳の立上げ支援
- 予防:消耗・環境に応じた予防保全提案(交換の前倒しで長期コスト最適化)
写真1~2枚でOK:全景/レール部/気になる箇所。現状の緊急度と概算の目安を無料でご案内します。

まとめ(今日から回せる“型”を手に入れる)
シャッターのメンテナンス点検項目は、固定化→記録→比較の流れで初めて効果を発揮します。
点検の型ができると、突発故障は減り、安全性は上がり、結果的に修理総額も縮小します。
まずは本コラムで記載させていただいた日常カード/月次票を印刷し、1か月だけ回してみてください。
きっと、見える景色が変わります。
- 要点
- 安全最優先(電気・高所・バネ・分解はプロへ)
- 日常/月次/半期・年次の三段で点検項目を固定化
- 写真・所見の一元管理で“いつもと違う”を早期発見
- 環境イベント後は臨時点検(台風・豪雨・塩害・粉じん)
- 防火設備は法定点検(有資格者手配&報告まで)
- 安全最優先(電気・高所・バネ・分解はプロへ)
なお、「この音は様子見で良い?」「この配線、危なくない?」「点検票を一緒に作りたい」など、シャッターのメンテナンスについて気になったことがあれば、シャッター119にご相談ください。
どのタイミングのご相談でも大歓迎です。
関西全域で、無料現地診断・見積り、写真ベースの事前アセスメント、一次復旧から恒久修繕・法定点検まで一気通貫で伴走します。
迷ったら止める・呼ぶ・記録する。これが設備を守り、人を守る最短ルートです。シャッター119が、現場を止めない最適解をご提案します。
【ご依頼の流れ】
- 点検:まず、シャッターの損傷箇所を点検します。
- 見積もり:修理にかかる費用を見積もります。
- 修理:必要な部品を交換し、シャッターを修理します。
- 動作確認:修理後、シャッターが正常に動作するか確認します。
修理は、必ず依頼いただいたお客様とお話し、ご納得いただいた上で開始させていただきます。
「当初の見積もりよりも部品の発注をしないといけなくなりそう」「費用がかかりそう」だと判断した場合は、必ず手を止めて再度ご提案をさせていただきます。
いきなり修理を始めて、修理後にビックリする金額を請求するようなことはございませんのでご安心ください。

この記事の著者

シャッター119 編集部
シャッターに関するお役立ち情報を発信しています。代表の私が長年の経験に基づき、修理費用の目安、業者選びのポイント、日々のメンテナンス方法などを簡潔に解説。シャッターに関する疑問を、スピーディーに解決します。シャッターの修理・交換も「シャッター119」にお気軽にご相談ください♪