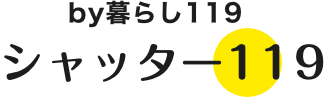シャッターの錆を予防する方法。塗装・清掃・潤滑の正しい手順で“長持ち・静か・キレイ”を実現
修理・交換2025.08.24
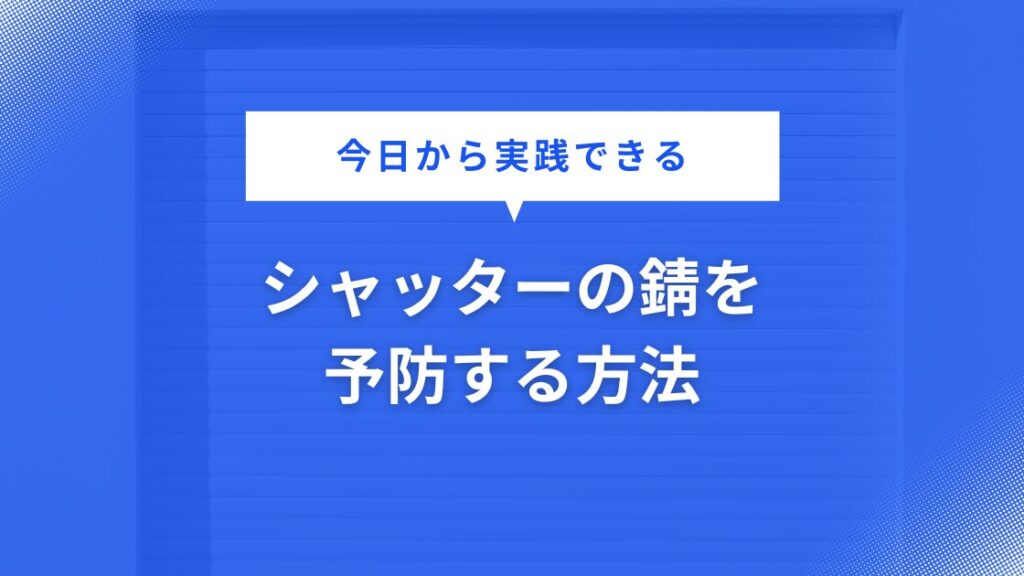
シャッターの“サビ”は、見た目の問題にとどまりません。
ザラつき、色ムラ、赤茶けた縁取りなど、その小さな変化は、動きが重い・異音が出る・固着する・最悪は穴あきや部材破断へとつながる“予兆”です。
関西は梅雨の長雨・台風・黄砂・大阪湾の潮風など、サビが進みやすい条件がそろっています。
放置が長引くほど対処は大掛かりになり、費用も指数関数的に跳ね上がります。
とはいえ、毎日完璧なお手入れは現実的ではありません。大切なのは、月次・季節・年次の3層で無理なく回せる予防ルーティンを持つこと。
本コラムでは、業務用・大型シャッターを対象に、今日から実践できるサビ予防の手順をプロ目線でわかりやすく解説します。
- サビが起こる仕組みと、関西で進みやすい“環境要因”
- 清掃→乾燥→潤滑/防錆→塗装の正しい順番と頻度
- 摺動部は乾式シリコン、非摺動部は防錆ワックス―失敗しない使い分け
- 材質別(スチール/アルミ/ステンレス/亜鉛メッキ)の注意点
- DIYでできることとプロに切り替える基準(高所・広範囲・構造腐食・動作不良)
- 梅雨前・台風後・黄砂期に効く“関西版”季節カレンダーと月次チェック表
- 軽度・中等度・重度の進行度別の初期対応と費用レンジの考え方
読み終えたとき、必要な対策を迷いなく、最短ルートで選べるはずです。
シャッターが錆びる原因とは?(仕組みとリスクを先に知る)
サビ対策の近道は、なぜ錆びるのかを知ることです。
原因が分かれば、打つべき手はシンプルになります。
ここでは、サビの発生メカニズム・環境要因・放置リスクを整理。
特に関西で目立つ塩害・湿気・粉塵の影響も具体化します。
「まだ軽いから大丈夫…」となりがちな段階こそ、予防コストが最小です。
基礎を押さえて、次章の実践に進みましょう。
サビ(腐食)のメカニズムを30秒で
金属(主に鋼板)が水分・酸素・塩分と反応して、酸化物(赤錆/褐色)が生成されます。
微小な傷・塗膜のピンホール・溜水が起点となり、電位差が生まれると局所から急速に進行。
「見えない裏側」やレール底・折り返し部など、水と汚れが滞留する部位ほど要注意です。
錆びやすい環境・条件(関西の実情)
海沿い(大阪湾・神戸・和歌山沿岸)は飛来塩分で塩害リスクが高く、梅雨〜台風期は湿潤環境で加速します。
黄砂・花粉(京都・滋賀・奈良)はレール溝で水分と混じり「泥だまり」を作り、乾湿の繰り返しで腐食促進。
幹線道路沿いの排ガス・油膜、工場周辺の粉塵も付着汚れの“栄養源”。
清掃頻度が最大の差になります。
放置リスク(費用は指数関数的に上がる)
サビは動作抵抗の増加→異音→引っかかり→固着・穴あきとエスカレートします。
レール・スラットの摩耗・波打ち、駆動部の負荷増→電動ならモーター劣化も連鎖。
結果、軽微補修(数千〜数万円)→部材交換(数万〜十数万円)→一式更新(数十万円〜)と、対処が重くなります。
初期の“汚れ除去+乾式潤滑+防錆皮膜”で止めるのが、最短・最安です。
シャッターの錆を予防する基本方法(今日から回せる3レイヤー)
サビ予防は①汚れをためない ②水分を残さない ③保護皮膜で守るの3レイヤーが基本です。
この章では、日常清掃・湿気対策・潤滑/防錆・塗装の正しい順番と頻度を、失敗しやすいポイント込みで解説します。
まずは清掃と乾燥。次に適材適所の皮膜づくり。
これだけで大半のサビは“未然に”抑えられます。
日常清掃と点検(頻度:月1/砂・黄砂期は月2)
レール溝・スラット端・下端ゴム周りの砂・泥・落葉をブラシ→掃除機で除去。
中性洗剤で拭き洗い→完全乾燥が鉄則。水気が残ると逆効果です。
目視で塗膜の傷・膨れ・点錆をチェックし、小さなうちにタッチアップへ繋げます。
雨・湿気対策(梅雨・台風期は“乾かす仕組み”優先)
雨天や洗浄後は軽く開閉して水気を切り、布で下端・レールの水を拭き取ります。
排水経路(レール底の溝・外周の勾配)の詰まりを季節ごとに点検。
閉めっぱなしの長期放置は結露の温床。
月1回の換気・試運転で湿気を追い出しましょう。
潤滑剤・防錆剤の“正しい使い分け”
摺動部(レール・スラット):乾式シリコンスプレーが基本。
乾いて薄い被膜を作り、ホコリを抱き込みにくいのが利点。
非摺動部(ボルト・ヒンジ外面・露出金属):防錆ワックス/防錆オイルを薄く。雨掛かり部はワックス系が長持ち。
※CRC-556等の油性潤滑は泥化→再発の原因になりがち。摺動部では避け、やむを得ず使用したら拭き上げてください。
塗装(錆止め塗料)で守る〈最も効く“予防打ち”〉
塗膜は酸素・水分・塩分から鋼板を守る最強のバリア。
数年おきの再塗装で効果を維持します。
基本は下地処理(ケレン・脱脂)→錆止めプライマー(エポキシ系)→上塗り(ウレタン/シリコン)。
タッチアップはDIY可。ただし広範囲・高所はプロへ。
塗り重ね乾燥時間を守ると耐久性が段違いです。
設置環境に応じた追加対策(関西版)
海沿い:耐塩害塗料+洗い流し頻度アップ。台風後は即洗浄・乾燥。
黄砂/粉塵環境:レール溝の乾式清掃→乾式シリコンの頻度を上げる。
幹線道路沿い:油膜・煤は中性洗剤で分解→拭き上げ→防錆で再付着を抑制。
材質別のサビ予防ポイント(同じ“金属”でも挙動が違う)
シャッターはスチールが主流ですが、アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ(ガルバ)も使われます。
材質ごとに腐食の出方・適した塗料・禁忌が違うため、この章で要点を押さえましょう。
迷ったら中性洗剤・乾式潤滑・防錆ワックス薄塗りは共通安全策です。
スチール(鋼板)—最も錆びやすい。だから基本を忠実に
水分と塩分に弱く、傷・折り曲げ部から発錆。
ケレン→エポキシ錆止め→上塗りが基本形。
レール底は乾式で汚れを抱き込まない。
切断端部のシーリングやタッチアップで“点”の発生を封じます。
アルミ—赤錆は出にくいが、白錆・塗膜劣化に注意
アルミは酸化皮膜で保護されますが、アルカリ性汚れや異種金属接触で腐食が進むことがあります。
中性洗剤での優しい洗浄→乾燥→専用プライマーが有効。
研磨はやりすぎ禁物。
鉄部と直接接触しないよう、絶縁テープ・シーラーで電食を防止。
ステンレス—もらい錆とすきま腐食を回避
ステンレスは錆びにくいが、もらい錆(鉄粉付着)やすきま腐食には注意。
定期洗浄→水切り→乾燥で美観維持。研磨傷はヘアラインを乱さぬ方向で。
塩分環境では洗い流し頻度を上げると安心です。
亜鉛メッキ(ガルバ)—下地選びがカギ
新しいメッキ面は密着しにくいので、メッキ対応プライマーを選定。
白錆が出始めたら優しく除去→中性洗浄→完全乾燥。
上塗りはシリコン/フッ素系など耐候性の高いものが長持ちです。
DIYでできること vs プロに任せるべきこと(安全と仕上がりの線引き)
“自分でできる範囲”を押さえれば、小コストで効果大の維持管理が可能です。
一方、高所・広面積・構造部の腐食・動作不良を伴う場合は、プロの出番。
ここでは、判断を迷わないための安全基準と依頼目安を明確にします。
DIYでできる主な予防メニュー(安全圏)
外側・見える・届く範囲の作業に限定します。
- レール溝の乾式清掃(ブラシ/掃除機)
- 中性洗剤→拭き洗い→完全乾燥
- 乾式シリコンで摺動部の潤滑
- 防錆ワックスの薄塗り(非摺動部)
- 点錆タッチアップ(ケレン→錆止め→上塗り)
※脚立は介助者付き、保護具(手袋・ゴーグル・マスク)着用が前提。
プロに任せるべきケース(迷ったら“止めて相談”)
- 広範囲の塗り替え・高所作業(足場・高所作業車が必要)
- 穴あき・波打ち・構造部の腐食(強度低下の恐れ)
- 動作不良・異音を伴うサビ(駆動・電装に波及)
- 防火シャッター・大型重量シャッター(法的・安全要件)
根本処置・保証・再発予防まで含めて、結果的に安価になるケースが多いです。
依頼の流れと費用感(目安)
- 無料相談(症状・環境のヒアリング)
- 現地診断・見積(状態・作業範囲・工期の提示)
- 施工(清掃・下地・錆止め・上塗り/部材交換)
- 再発予防のメンテ計画をご提案
費用は規模で変動しますが、総合メンテ(清掃・潤滑・小補修)数千〜数万円/部分塗装 数万円台/広範囲塗装・部材交換 十数万円〜が一般的なレンジです。
錆対策・塗装はプロに任せると“安全・確実・長持ち”です。
シャッター119は関西全域で無料相談・出張見積もりに対応。状態確認だけでも歓迎です。
塗装で錆を予防:もう一歩踏み込む実践ガイド
「せっかく塗るなら、長持ちさせたい」。そのための時期・手順・材料選定を凝縮しました。
DIYでも、手順の抜け・焦りをなくせば仕上がりが安定します。
安全最優先で、無理な高所と広面積はプロへ切り替えましょう。
●塗り替えのタイミングと季節
- 目安:新設後3〜5年、もしくは前回塗装から5〜7年で点検・再塗装検討
- 季節:春・秋(湿度50〜65%・15〜25℃)が理想。梅雨・真冬は乾燥不良リスク
- サイン:色あせ・チョーキング・ツヤ低下・点錆が見えたら早めの手当て
●下地処理が“9割”を決める
- ケレン(ワイヤーブラシ/ペーパー)で浮きサビ・脆弱塗膜を除去
- 脱脂(中性洗剤/専用クリーナー)→完全乾燥
- マスキング(周辺養生)で仕上がりが一気に変わる
※錆を残したまま塗ると、下から再発します。焦らず丁寧に。
●塗料の選び方(現場で“効く”組み合わせ)
- 下塗り:エポキシ系錆止め(密着・防錆性能が高い)
- 上塗り:ウレタン/シリコン(価格・耐候のバランス)/フッ素(長寿命・高価)
- メッキ面:メッキ用プライマーを忘れずに
- 海沿い:耐塩害グレードの選定が安心
●塗装のコツと仕上げ
- 薄く均一に複数回(厚塗りは垂れ・乾燥不良の原因)
- 規定乾燥時間を厳守(下塗り→上塗りの間隔)
- 角・端部・折り返しは先に塗り、面は最後にのせる
- 施工後24時間は水濡れ・開閉の連続動作を避ける
「もう錆びている」場合の初期対応(進行度別)
既に錆が出ていても、進行度に応じた対処で回復できます。
この章では軽度・中等度・重度の目安と、DIYか専門かの判断材料を示します。
迷ったら写真を撮って相談が最短です。
●軽度(点錆・茶色の筋)—DIY可
- ケレン(#240〜320)→粉塵除去→錆止め→上塗り
- 周辺まで少し広めに下塗りして浸食を止める
- 仕上げ後は防錆ワックス薄塗りで保護
●中等度(膨れ・塗膜浮き・部分的な波打ち)—部分補修+要診断
- 浮き範囲を取り切る→段差をパテ整形→錆止め→上塗り
- 内側やレール側の腐食が疑われるため、プロ診断推奨
- 早めに止めれば部材交換回避の可能性大
●重度(穴あき・広範囲・強い波打ち)—交換・補強の検討
- スラット交換・レール交換・一部更新が現実的
- 強度低下・落下リスクも伴うため、即運用停止→専門対応
- 施工と同時に再発予防の塗装・メンテ計画を組む
季節と環境で変える“関西版”メンテ計画(カレンダー付き)
計画があればメンテナンスも続けることができます。
月次・季節・年次の3層で“無理なく回る”スケジュールを目指してみてください。
海沿い・内陸・工業地帯など、立地ごとに強めるポイントも併記しました。
紙1枚のチェックリストでも効果は抜群です。
標準カレンダー(例)
- 毎月:レール清掃/目視点検/試運転
- 梅雨前(5〜6月):徹底洗浄→乾式潤滑→排水経路点検
- 台風後:即洗浄→乾燥→点検(歪み・緩み)
- 黄砂期(春):清掃頻度増/レール泥だまりをゼロに
- 年1回(多頻度は年2回):総合点検・小補修・タッチアップ
- 塗装検討:3〜5年に一度、状態を見て計画
立地別の強化ポイント
- 海沿い(大阪湾・神戸・和歌山):洗い流し頻度↑/耐塩害塗装
- 内陸(京都・奈良・滋賀):黄砂・花粉シーズンの乾式清掃↑
- 幹線道路・工場周辺:油膜除去→防錆のルーティン化
よくある失敗(やってはいけないこと10)
失敗は再発・悪化・高コスト化の近道。ここだけは避けましょう。
当てはまるものがあれば、その場で中止→相談が安全です。
- 高圧洗浄で水を押し込み、電装・ベアリングに浸水
- 油性潤滑の厚塗りでホコリを泥化→再発
- 錆の上から塗装(下から再発)
- 乾燥不足のまま上塗り(密着不良・ふくれ)
- 異種金属を直にボルト接合(電食)
- 排水経路の放置(レール底の水たまり)
- 閉めっぱなしの長期放置(結露・固着)
- 脚立の単独作業(転落リスク)
- ボックス内・バネ・駆動に触る(重篤事故)
- 防火シャッターの独自改造(法令・安全違反)
ケーススタディ(関西の現場から)
環境と使い方で、打ち手は変わります。典型例×解決策を3件ご紹介。
どのケースも、早期の正しい対処が効きました。
(1)大阪湾岸・路面店:スラット下端の点錆が拡大
潮風+自動ドアとの兼用で下端に点錆。放置で縦筋へ拡大。
徹底洗浄→ケレン→エポキシ錆止め→上塗り→防錆ワックスで復旧。
台風後洗浄と季節点検を組み、以後は安定運用。
(2)京都市・倉庫:黄砂期のレール固着
レール溝に黄砂+雨水が泥状に堆積。動作重い→異音へ。
乾式清掃→中性洗浄→完全乾燥→乾式シリコンで軽快化。
春の清掃頻度UPの運用ルール化で再発なし。
(3)兵庫内陸・工場:広範囲の色あせと白錆
粉塵と朝露で塗膜が劣化、一部メッキ面は白錆。
メッキ対応プライマー→高耐候上塗りで全面塗替え。
年2回総合点検と開閉回数の管理で保全レベルを底上げ。
まとめ(要点と次の一手)
サビ予防は、汚れをためない/水分を残さない/皮膜で守るの3本柱が全てです。
中性洗浄→完全乾燥→乾式潤滑→防錆ワックス→必要に応じて塗装。これが王道フロー。
関西の梅雨・台風・黄砂・海風を前提に、月次・季節・年次の三層で運用すると再発を抑えられます。
迷ったら止めて相談。
広範囲・高所・構造腐食・動作不良は、プロが最短・最安で解決します。
- 今日やる:レール清掃/下端拭き上げ/乾式シリコン
- 今月やる:点錆タッチアップ/排水経路点検
- 今季やる:梅雨前の徹底洗浄と乾燥、必要なら塗装計画
なお、シャッター119は、関西全域(大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀)で無料診断・出張見積もりに対応します。
サビの進行度チェックから、最小コストで効果の高いメンテ・塗装・交換プランまで、現地でご提案。
緊急の不調もご相談ください。
まずは状態の見える化(写真・動画)だけでOKです。
「設置場所/環境(海沿い・幹線沿い等)」「症状(写真)」「直近の清掃・塗装履歴」をお伝えいただくと、最短ルートでご案内できます。
今日の一手で、明日のトラブルを未然に。お気軽にお声がけください。
【ご依頼の流れ】
- 点検:まず、シャッターの損傷箇所を点検します。
- 見積もり:修理にかかる費用を見積もります。
- 修理:必要な部品を交換し、シャッターを修理します。
- 動作確認:修理後、シャッターが正常に動作するか確認します。
修理は、必ず依頼いただいたお客様とお話し、ご納得いただいた上で開始させていただきます。
「当初の見積もりよりも部品の発注をしないといけなくなりそう」「費用がかかりそう」だと判断した場合は、必ず手を止めて再度ご提案をさせていただきます。
いきなり修理を始めて、修理後にビックリする金額を請求するようなことはございませんのでご安心ください。

付録:サビ予防チェックリスト(印刷して現場掲示OK)
運用を仕組み化すると、品質は安定します。
下記を月次点検票としてお使いください。
担当が変わっても回るフォーマットです。
月次点検(□は実施・異常時は備考に記入)
- □ レール溝の乾式清掃(砂・落葉・黄砂の除去)
- □ 中性洗浄→拭き上げ→完全乾燥
- □ 摺動部の乾式シリコン(薄く/床の拭き取り)
- □ 非摺動部の防錆ワックス(薄く)
- □ 点錆・塗膜の膨れ・傷の有無/タッチアップ
- □ 排水経路の詰まり・下端ゴムの水溜まり有無
- □ 目視での歪み・緩み・異音の有無(※異常時は即中止・相談)
季節・年次(運用カレンダー)
- 春(黄砂期):清掃頻度UP/レール泥だまりゼロ化
- 梅雨前:徹底洗浄→乾燥→乾式潤滑/排水経路点検
- 台風後:即洗浄→乾燥→歪み・緩み点検
- 年1(多頻度は年2):総合点検・小補修・タッチアップ/塗装要否判定
重要な安全メモ(最後まで大切に)
- 電動は必ず電源OFF。ボックス内・バネ・駆動・電装には触れない。
- 高所作業は2名以上・適切な足場。脚立単独は避ける。
- 洗浄・塗装は換気と火気管理。溶剤の取り扱いはSDSに従う。
- 高圧洗浄・油性厚塗り・錆の上塗りはトラブルのもと。やらない。
- 迷ったら止めて相談。それが最短・最安・最安全です。
この記事の著者

シャッター119 編集部
シャッターに関するお役立ち情報を発信しています。代表の私が長年の経験に基づき、修理費用の目安、業者選びのポイント、日々のメンテナンス方法などを簡潔に解説。シャッターに関する疑問を、スピーディーに解決します。シャッターの修理・交換も「シャッター119」にお気軽にご相談ください♪