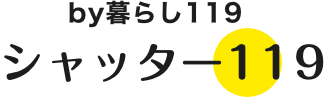シャッターのメンテナンスに「資格」は必要?業者選びで失敗しないための完全ガイド
修理・交換2025.09.26
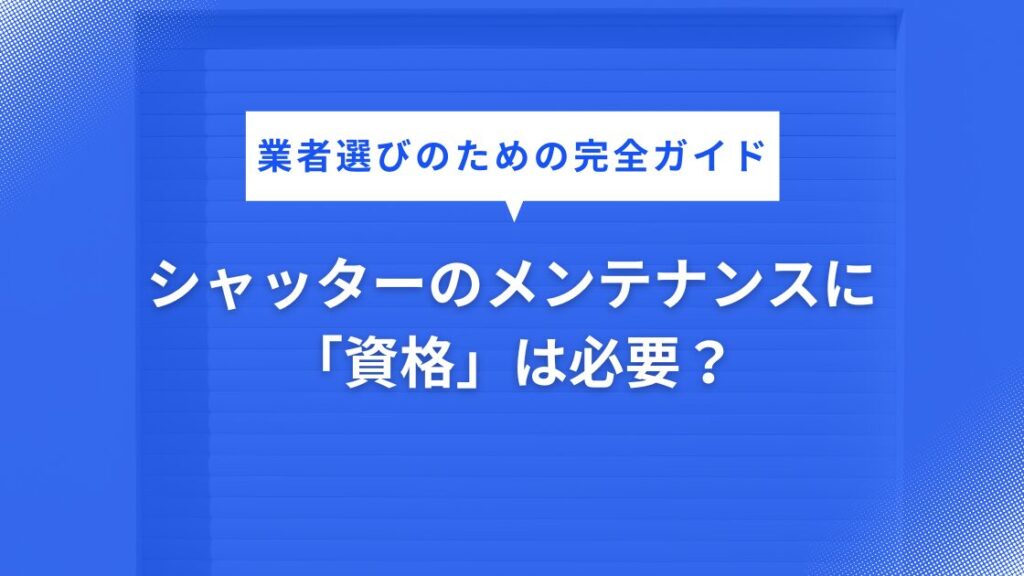
「定期メンテナンスをしたいけれど、資格のある業者に頼むべき?」「電動シャッターのモーター交換や配線に資格はいるの?」「防火シャッターの法定点検は誰に頼めばいい?」
関西(大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀)で毎日シャッターを使うオーナー様・管理者様から、私たちに寄せられるご相談の多くは“資格や法令”に関する疑問です。
費用だけで選ぶと、あとで「そもそも有資格者でないと触れない作業だった」と判明し、やり直しや追加出費になることも少なくありません。
本コラムは、「どの作業に資格が必要か」「資格が不要でも“あったほうが良い”根拠」「防火シャッターの法定点検の正しい依頼先」「安全に作業するための労働安全衛生の講習」まで、業務用・車庫・店舗向けシャッターの“資格とメンテナンス”を体系的に整理します。
お読みいただいた後は、自分の現場で必要な資格を自信をもって見極め、失敗しない業者選びができるようになります。
ぜひ最後までお読みください。
シャッターメンテナンスに資格は必要?
「資格がないと何もできない」わけではありません。
日常清掃や潤滑などの軽微な保全は資格不要で行えます。
一方で、電気配線に触れる作業や法令に基づく検査・報告、高所や機械を扱う作業は、国家資格や法定講習が関係します。
ここを押さえておくと、無資格施工のリスクや余分なやり直しを避けられます。
要点:
- 資格不要:レール清掃、外観点検、シリコン系潤滑剤の軽い塗布、ボルトの目視・軽い増し締め(構造や安全装置を損なわない範囲)。
- 資格が関係:
- 電動シャッターの電気工事(低圧配線/機器接続) → 原則「電気工事士」の業務領域。とくに第二種で一般用電気工作物の工事をカバーします。
- 防火シャッターの“法定”定期検査と報告 → 「防火設備検査員」など、建築基準法に基づく有資格者が実施・報告する仕組み。
- 高所作業車の運転・昇降機器の使用、フルハーネス着用作業 → 労働安全衛生法に基づく技能講習/特別教育が必要。
- 電動シャッターの電気工事(低圧配線/機器接続) → 原則「電気工事士」の業務領域。とくに第二種で一般用電気工作物の工事をカバーします。
日常の軽メンテは自社でもOK。
ただし「電気」「法定点検」「高所・機械」が絡む作業は有資格者の領域です。
防火シャッターの法定点検と「防火設備検査員」
防火シャッター(防火設備)は、建築基準法第12条に基づく定期報告制度の対象です。
対象建築物では所定の周期で定期検査・報告が求められ、原則は有資格者が検査を実施します。
とくに不備があると、非常時に確実に閉鎖しないなど重大なリスクがあるため、資格と制度を正しく理解しましょう。
法定点検の枠組み(建築基準法第12条:定期報告制度)
- 対象:一定規模・用途の建築物に設置された防火設備(自治体告示で具体化)。
- 頻度:自治体や設備区分に応じて毎年(年1回)等の周期で報告。最新の改正や自治体運用で、設備の種類により1~3年の検査周期となるケースにも留意。
- 依頼先:定期調査・検査を行える資格者(防火設備検査員 ほか)に依頼し、所定様式で報告します。
「防火設備検査員」とは?
- 位置づけ:国土交通省の制度に基づく国家資格。防火設備の定期検査・報告を行うための必須資格として整備されています。
- 依頼メリット:報告の適法性が担保され、検査記録の整備や是正提案までワンストップ。自治体の指導対応もスムーズです。
管理者の実務は台帳管理(設置場所・台数・型式)→検査スケジュール化→是正履歴の保存。
法定点検は「年次イベント」ではなく「安全を維持する運用」と捉えましょう。
電動シャッター×電気工事—どこから「電気工事士」の仕事?
電動シャッターのモーター交換・制御盤更新・配線改修は、低圧回路であっても電気工事士の業務に該当します。
リモコン電池交換や操作設定の範囲なら資格不要ですが、電源回路に触れる作業は原則アウト。
保安と事故防止の観点からも、有資格者の施工を基準にしましょう。
代表的な“要・電気工事士”の例
- モーター交換/制御盤(リレー・基板)交換:動力配線の接続・絶縁処理・試運転。
- 電源分岐・延長・コンセント新設:建築側の電源や幹線に関わる可能性。
- 安全装置(リミット・光電センサー等)配線:誤結線は重大事故につながり得ます。
→ 第二種電気工事士が一般用電気工作物(低圧)の配線・接続を扱える制度です。
DIYでやってよい範囲
- リモコンの電池交換、操作パネルの時刻設定、非常開放の復帰操作(取説に準拠)など。
※ただし、カバー内(活線部)には手を入れないのが鉄則。
“動力が絡む=電気工事士”と覚えておくと判断を誤りません。
安全に作業するための「技能講習・特別教育」
シャッターは高所・重量・回転体と隣り合わせ。
現場での安全対策は、資格の有無と同じくらい重要です。
実務では高所作業車やフルハーネスの資格・教育が求められます。
労働安全衛生法に基づく講習・教育の有無は、業者選びのチェック項目に必ず入れてください。
高所作業車運転技能講習(作業床10m未満含む区分あり)
- 内容:高所作業車の運転・操作に必要な技能講習(機体の安定・救出手順等)。
- 根拠:労働安全衛生法に基づく技能講習区分。
フルハーネス型墜落制止用器具の特別教育
- 内容:フルハーネスの正しい選定・装着・落下時の身体影響等。
- 根拠:厚生労働省が特別教育の実施を義務づけ。
※補足
現場によっては足場の組立て等特別教育、有機溶剤作業などが必要な場合も。
現場リスクに応じて教育が実施されているか、安全衛生計画書やKY記録の有無も確認しましょう。
資格だけでは足りない?関西で失敗しない「業者選び」チェックリスト
“資格保有=良い業者”とは限りません。
体制・記録・保険まで含め、安心して任せられる会社かを総合評価しましょう。
以下のチェックを見積り前に照らし合わせれば、価格比較だけでは見えない差がわかります。
チェックポイント
- 資格の明示:防火設備検査員/電気工事士/高所作業車・フルハーネス受講歴の在籍状況。
- 報告書・記録:点検チェックリスト・写真台帳・是正提案の標準付帯。
- 法定点検の対応範囲:建築基準法の定期報告を想定した書式対応と自治体運用の理解。
- 第三者賠償保険:施工不良・事故時の補償枠(対人・対物)。
- 在庫と機動力:よく出る消耗品(スプリング・スラット)やモーターの即応在庫/当日~短期調達。
- 緊急対応時間:営業時間外・夜間の呼び出し可否、復旧優先の暫定措置が可能か。
- 見積の透明性:出張・点検・作業・部材の区分明細、写真ベースの必要性説明。
【事例で理解】この作業は誰に任せる?(判断早見表)
「自社でやる」「一般の施工店に頼む」「有資格者に頼む」の境目を、よくある作業で具体化しました。
迷ったら安全側に倒して判断してください。
- レール清掃・外観点検・軽い潤滑:自社対応(資格不要)。
- スラット軽補修(歪み直し・端部成形):専門業者(無資格でも可だが経験重視)。
- モーター交換・制御盤更新・配線延長:電気工事士(第二種以上)在籍の業者。
- 防火シャッターの定期検査・報告:防火設備検査員に依頼。
- 高所作業車での上部ユニット整備:高所作業車運転技能講習修了者+フルハーネス特別教育。
シャッター119の体制(関西全域)「資格×機動力×説明力」で安心をお届けします!
シャッター119は、関西全域(大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀)で24時間365日の緊急受付・最短即日出張(スケジュール枠による)に対応。
電気工事士・防火設備検査員(提携含む)・高所作業車/フルハーネス受講者によるチーム体制で、安全・確実・わかりやすい説明を徹底しています。
- 無料の現地診断・見積もり(点検結果と写真付き報告)。
- 一次復旧→恒久修繕までの段階提案で、止められない現場も守る。
- 在庫・調達ネットワークで、定番モーター・スプリング・スラットにスピード対応。
- 法定点検(防火設備)は所定書式での報告整備に対応。
まずは状況だけでもお聞かせください。
写真1~2枚があれば、概算や緊急度の目安を当日中にご案内できます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)
資格や法定点検に関する“勘違いポイント”を中心に、短く要点でお答えします。
判断の拠り所としてお役立てください。
Q1. 日常の点検・清掃に資格は要りますか?
A. 不要です。レール清掃・外観点検・軽い潤滑は自社で実施できます。ただし安全装置・電気配線・高所機器に触れないのが条件です。
Q2. 電動シャッターのモーターを自分で交換しても良い?
A. 推奨しません。電気工事士の業務領域です。誤結線は感電・焼損・誤作動のリスクがあります。
Q3. 防火シャッターの点検は“年1回”が絶対?
A. 建築基準法の定期報告制度に基づいて周期が定められ、自治体運用や設備区分で1~3年の幅があるケースもあります。該当建物の告示・要綱をご確認ください。
Q4. 防火シャッターの検査は誰でもできる?
A. 原則、防火設備検査員などの有資格者が行います。国家資格として運用され、検査・報告の適法性が担保されます。
Q5. 高所作業車やフルハーネスに講習は必要?
A. はい。高所作業車は技能講習、フルハーネスは特別教育が必要です。受講歴のあるスタッフが担当する業者を選んでください。
メンテナンス運用のためのテンプレート
資格以前に“運用”で差がつきます。
以下のテンプレートを月次/年次で回せば、点検漏れや法定報告の失念を防げます。
ぜひ社内でそのままコピペしてお役立てください。
月次(現場担当)
- レール清掃・落葉除去(5~10分/台)
- 開閉テスト(途中停止・異音チェック)
- 目視点検(錆・歪み・固定ネジの緩み)
- 不具合の一次報告(写真添付・発生日)
半期(設備担当)
- 潤滑ポイントの一括ケア(シリコン系)
- 消耗部の劣化傾向レビュー(前回写真と比較)
- 高頻度使用シャッターの予防保全(事前部材手配)
年次(管理者)
- 防火設備の定期検査(対象建物のみ)のスケジューリング・発注
- 主要シャッターの総合点検(電気・機械・安全装置)
- 修繕計画・費用化(故障前の予防交換を含む)
まとめ
日常の軽メンテは自社で十分。
一方で、電気工事・防火設備の法定点検・高所機器の運用は、有資格者の領域です。
この線引きを押さえ、記録と計画で回すほど、突発故障・事故・法令対応のリスクは下がります。
要点の再整理
- “電気・法定・高所”=有資格者に依頼する。電動は電気工事士、防火は防火設備検査員、高所は技能講習/特別教育。
- 資格だけでなく、記録・説明・保険・機動力で業者を選ぶ。
- 運用テンプレで“点検忘れ”をなくす。予防保全が最終的にコストを最小化。
なお、シャッター119では、「この作業は資格が要る?」「まずは状態を見てほしい」など、小さな疑問でも大歓迎です。
写真を添えていただければ、当日中の概算回答も可能です(状況により変動)。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
【ご依頼の流れ】
- 点検:まず、シャッターの損傷箇所を点検します。
- 見積もり:修理にかかる費用を見積もります。
- 修理:必要な部品を交換し、シャッターを修理します。
- 動作確認:修理後、シャッターが正常に動作するか確認します。
修理は、必ず依頼いただいたお客様とお話し、ご納得いただいた上で開始させていただきます。
「当初の見積もりよりも部品の発注をしないといけなくなりそう」「費用がかかりそう」だと判断した場合は、必ず手を止めて再度ご提案をさせていただきます。
いきなり修理を始めて、修理後にビックリする金額を請求するようなことはございませんのでご安心ください。

この記事の著者

シャッター119 編集部
シャッターに関するお役立ち情報を発信しています。代表の私が長年の経験に基づき、修理費用の目安、業者選びのポイント、日々のメンテナンス方法などを簡潔に解説。シャッターに関する疑問を、スピーディーに解決します。シャッターの修理・交換も「シャッター119」にお気軽にご相談ください♪