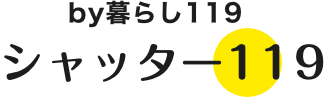【徹底解説】シャッターのグリス選び方と使い分け
修理・交換2025.10.27
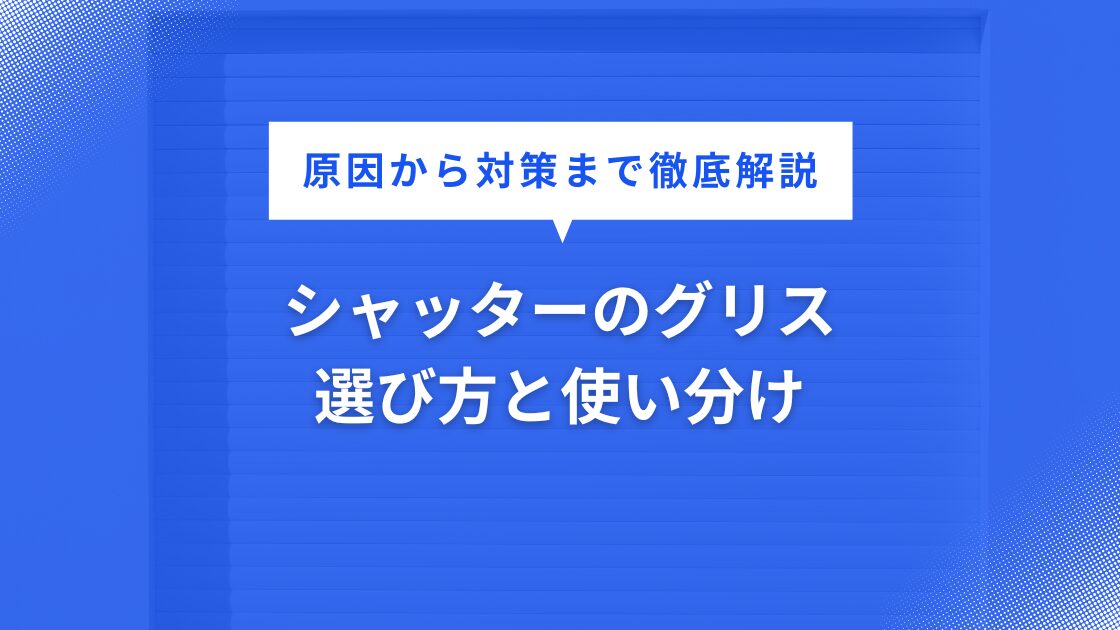
シャッターの動きが渋い、異音がする、早朝にキュッと鳴く。
そんなとき、多くの現場で行われがちなのが「とりあえず油を差す」。
しかし、場所に合わない潤滑剤は、埃を抱き込み摩耗を加速させたり、ブレーキ面に回り込んで制動力低下を招いたり、樹脂部を膨潤させたりと、逆効果になることが少なくありません。
潤滑は“塗ること”ではなく、適材適所を決める設計行為です。
本コラムでは、シャッターの主な潤滑ポイント(軸受・ブラケット・チェーン/ベルト・ギア・スプリング・レール接触部)ごとに、使うべき/使ってはいけない潤滑剤を明確化し、グリスの種類(増ちょう剤・基油の粘度・NLGI等級)まで踏み込みます。
さらに、関西特有の塩害・黄砂・台風・温湿度差といった環境条件を織り込み、選定→塗布量→再給脂周期→清掃の順番を現場で使える手順に落とし込みます。
「ガイドレールはシリコン薄膜、軸受は用途別グリス、ブレーキ面には絶対に回さない」
この基本を軸に、長持ち・静音・安全の3つを同時に実現しましょう。
まず押さえるべき“潤滑剤の適用範囲”
グリスの選定に入る前に、潤滑剤の適用範囲を大づかみに整理します。
間違えると、埃の吸着→摩耗増→停止という最短ルートに乗ってしまいます。
1. グリスが適する部位(滞留・封じ込めが目的の箇所)
グリスは基油(潤滑油)をゲル状に保持し、長く留まって潤滑・防錆するのが強み。
回転・すべり接触が局所に集中し、給脂間隔が長めの箇所に適します。
- 巻取り軸受(ブラケットのベアリング):荷重支持・回転。リチウム系やカルシウムスルホネート系が基本。
- アイドラーベアリング・ローラー:中速・不定期給脂にグリスは有効。
- オープンギア(露出ギア)/カム・ロック機構:粘着性(タック)のあるEPグリスが摩耗を抑制。
- スプリングの座・ピン:薄く防錆+微潤滑(過給脂は埃吸着)。
2. オイルが適する部位(浸透・洗い流し・冷却が目的)
オイルは流動性が高く、隙間への浸透・熱の持ち去りに優れます。
一方で飛散・滴下しやすいため、汚染に敏感な現場では注意が必要。
- チェーン(露出):本来はチェーンオイルが望ましい(粘度と付着性の調整済み)。グリスだまりはピン摩耗の元。
- 減速機(密閉型ギア):ギアオイル指定が基本(グリスは不可)。
- 油膜を薄く均一にしたい摺動:ドライPTFE系/低粘度シリコンオイルが○(ただしレールは後述の“薄膜”が原則)。
3. ドライ(乾式)・薄膜系が適する部位(粉じん・黄砂環境)
黄砂・粉じんが多い関西では、「ベタつくものを塗った場所=砂を集める場所」となります。
ガイドレールなど開口部に近い摺動面は、ドライ(PTFE)や無溶剤シリコンの薄膜で埃を抱き込まないメンテが鉄則。
- ガイドレール内面/スラット接触部:無溶剤シリコンスプレーを“ごく薄く”。CRC・グリスはNG。
- センサー近傍・安全装置周辺:ドライ系で“垂れない・飛散しない”ことが重要。
まとめとしては、以下の3つのポイントです。
- レールや開口近くの摺動=ドライ・薄膜(無溶剤シリコン、PTFE)。
- 軸受・ギア・ロック=グリス(用途に合わせた種類)。
- チェーン・密閉ギア=オイル(指定油)。
ここから先は、「どのグリスを選ぶか」を具体的に解説します。
グリスの基礎知識(増ちょう剤・基油粘度・NLGI・耐水・耐熱)
1. 増ちょう剤(石けん/非石けん)
グリスは基油+増ちょう剤でできています。
増ちょう剤は性能の根幹。
混合不可(原則)なので、異なる種類を足し合わせしないのが大原則。
- リチウム(複合リチウム):汎用性、耐熱・機械安定性に優れる。軸受に第一候補。
- カルシウムスルホネート:耐水・防錆・耐荷重(EP)に強い。沿岸・台風多発エリアに好適。
- アルミ複合:機械安定性・耐水良好。食品グレード(NSF H1)にも多い。
- ポリウレア:酸化安定性・長寿命。高温・密封機器に。
- ベントナイト・PTFE:非石けん系。耐熱やドライ寄り特性。混用厳禁。
2. 基油の粘度(ISO VG)
基油粘度は油膜の厚さ・低温起動性を支配します。
低速・高荷重=高粘度、低温起動・軽負荷=低粘度が目安です。
- 軸受一般(低~中速):ISO VG 100~220
- 高荷重(重量シャッター・端軸受):VG 220~320
- 低温(冬季朝一・冷凍周辺):VG 68~100
3. NLGI等級(硬さ)
NLGIは#000~#3で表し、数字が大きいほど硬くなります。
シャッターでは#1~#2が使いやすいです。
- #1:低温・供給ライン・少量塗布に〇
- #2:汎用。滴下しにくく保持できる
4. 耐水・耐塩・防錆
大阪湾・和歌山沿岸・台風時の吹き上げでは、耐水・耐塩が耐久性に直結します。
- 水洗い流し試験(ASTM D1264):数%以下だと耐洗浄性良好
- 防錆(ASTM D1743):錆発生なしが望ましい
- 耐荷重(四球EP試験):高荷重部には高数値が安心
ポイントは増ちょう剤は“混ぜない”。
新グリスに切り替える場合は、古いグリスを完全除去(パージ)してから充填します。
部位別・用途別のグリス選定
ここからは、シャッターの潤滑ポイントごとに「推奨グリス」「避けるべきもの」「塗布の量・頻度」「注意点」を具体化します。
1. 巻取り軸受(ブラケットのベアリング)
回転支持の要です。
異音・温度上昇・ガタは、軸受潤滑の劣化や不足が疑わしいサインです。
- 推奨:複合リチウム#2/ISO VG 150~220の汎用軸受グリス。沿岸・耐水重視ならカルシウムスルホネート#2。
- 避ける:粘土系・混用不可の特殊グリス(既存と不適合。混ぜない)。
- 量:“1/3~1/2充填”が基本。入れ過ぎは発熱・攪拌抵抗で寿命短縮。
- 周期:年1回点検/高頻度運用・粉じん環境は半年。
- 注意:防塵シール破損・水の侵入があると、どのグリスでも保たない。原因是正が先。
2. ローラー・アイドラーベアリング
中~軽荷重の回転部です。
水・粉じんの影響を受けやすい部位です。
- 推奨:リチウム#2/VG100~150。屋外・洗浄多ならカルシウムスルホネート#2。
- 量:少量・複数点に分けて。押し出されるまで詰めない。
- 注意:シールに相溶な基油を選び、NBR/EPDMの膨潤リスクを避ける。
3. オープンギア(歯車)・カム・ロック機構
露出歯車は、点接触・圧力集中が起こりやすいです。
- 推奨:タック性のあるEPグリス(リチウムorカルシウムスルホネート)#2。固着防止にモリブデン(MoS₂)微量添加品も有効。
- 避ける:サラサラ系・オイル単体(飛散・滴下で汚染)。
- 量:薄く全面に。山盛りにすると攪拌抵抗・飛散が増える。
- 注意:鍵・ロック面に回すと噛み込みの原因。余剰は拭き取り。
4. チェーン(露出)/ベルト(歯付・平)
チェーンはピン・ブッシュ内部の油膜が命。
ベタベタしたグリス溜まりは摩耗・磨耗粉堆積を招きます。
- 推奨:チェーン専用オイル(低粘度で浸透→粘着性で保持)。
- 避ける:グリス塗り。埃を抱え、ローラ固着→歯飛びへ。
- 補足:ベルトは原則無給油。張り調整・清掃で管理。
- 注意:油滴下=ブレーキ面への回り込み厳禁。制動性能に直結。
5. スプリング(座・ピン)
バネ本体を油で包むのはNG(埃吸着)です。
- 推奨:薄く防錆系グリスを座・支点ピンにのみ。
- 注意:バネの張力調整は危険。グリス選定以前にプロ作業の領域。
6. ガイドレール・スラット接触部(摺動)
開口部に近い、最も埃を拾う場所です。
“薄い・乾く・付着しにくい”ものを選ぶのが正解。
- 推奨:無溶剤シリコンスプレー(乾式)をごく薄く→布で均す。
- 避ける:CRC・鉱物油・グリス。黄砂・粉じんの吸着源になり、重く・うるさくなる。
- 頻度:月1(環境により増減)。清掃→薄膜の順を守る。
実際の現場では「どれを、どこに、どれくらい」が分かれば9割の潤滑問題は解けます。
シャッター119はメーカーを横断した数多くの実績・ノウハウを持っていますので、電気・機械・潤滑をまとめて診断できます。
最短即日に「清掃→適正薄膜→重点給脂」の段取りをご用意することも可能です。
お気軽にお問い合わせください。

シーン別の“正しい塗り方”
1. 清掃→点検→給脂の順序を崩さない
潤滑は“塗る作業”の前に清掃と点検があります。
汚れの上に良いグリスを載せても、異物を閉じ込めるだけです。
手順:
- 清掃(掃除機→ブラシ→湿拭き→乾拭き)
- 目視点検(ガタ・錆・割れ・シール破損)
- 給脂(箇所別に適正グリスを“適量”)
- 余剰除去(はみ出し拭き取り)
- 短ストローク試験(上・下各1回)
2. “量”の目安(少なすぎず、入れ過ぎず)
グリスは少なすぎても多すぎてもダメです。
軸受は空間の1/3~1/2、歯面は全周に薄く、ピン点は米粒が適量です。
- 軸受:1/3~1/2充填。過充填は発熱・攪拌で寿命短縮。
- ギア:刷毛や注射器で薄く行き渡せる量。
- 点摩擦:米粒~爪先のサイズで十分。
- レール:**「塗った跡が分からないくらい」**が正解。
3. 周期(給脂・再点検)
使用頻度・環境で変わりますが、基準がないとズルズルと忘れがちです。
- 軸受:年1回/高頻度・粉じんは半年。
- ギア・ロック:半年~年1。
- レール薄膜:月1(黄砂・塩害は都度)。
- チェーン:専用オイルを月1~2(飛散・汚染に注意)。
4. 混用を避ける(切替時はパージ)
増ちょう剤の相性で、軟化・硬化・分離が発生します。
切替時は古いグリスを完全除去してから新グリスへを徹底してください。
- 目安:シンナーは原則禁止(樹脂・塗装を痛める)。ウエス・パーツクリーナー(樹脂対応)で拭き取り。
環境・衛生要件で変わる“選び方”
1. 食品・薬品工場(NSF H1/H3)
偶発的に食品に接触しても安全なNSF H1準拠のグリスが必要です。
アルミ複合やPAO基油が多いです。
- ガイド薄膜は無溶剤シリコン、チェーンはH1オイル。
- 滴下・飛散への配慮が最重要。
2. 低温(冷凍庫前・寒冷朝一)
低温で硬くならない低粘度基油(VG68~100)、NLGI#1寄りが起動性◎。
- ベアリング:低温用リチウム/ウレア。
- レール:乾式薄膜固定。
3. 塩害(大阪湾・和歌山沿岸)
カルシウムスルホネートが強力です。
防錆+耐水+EPを1本で賄えます。
- 清掃は真水→乾拭きを月1で。塩を残さないことが最重要。
4. 粉じん・黄砂(国道沿い・物流)
レール・開口部には油分を置かないこと。また、ドライ薄膜を徹底してください。
- 給脂周期は短め(粉じんで油膜が切れやすい)。
よくある“間違い”とその理由
1. レールにグリスやCRCをたっぷり塗る
最も多い誤りです。
埃・黄砂・塩分を抱き込み、重く・うるさくなります。
- 正解:清掃→無溶剤シリコン薄膜。“塗った感”が出ない程度に。
2. チェーンにグリスを塗る
ピン・ブッシュ内部に届かず、外側で固まって摩耗と歯飛びを誘発します。
- 正解:チェーン専用オイルで浸透→保持。
3. ブレーキ面に油が回る
制動性能低下=重大事故の恐れがあります。
- 正解:塗布位置の遮蔽・拭き取り、飛散抑制。
4. グリスの混合・継ぎ足し
増ちょう剤の相性問題で軟化・分離してしまう可能性があります。
- 正解:パージ→切替。銘柄・種類の管理を。
5. 入れ過ぎ
発熱・攪拌抵抗で寿命短縮につながってしまいます。
- 正解:量の基準を守る。軸受は1/3~1/2。
トラブルシューティング
現場で「どこに何を」がすぐ引けるように、ミニリファレンスを用意しました。
印刷して活用してください。
| 症状 | 疑う箇所 | 推奨潤滑 | 一次対応 |
|---|---|---|---|
| キー/ギー(摺動音) | レール・スラット | 無溶剤シリコン薄膜 | 清掃→薄膜→短ストロークで馴染ませる |
| ガタ/ガタン | ガイド固定・芯ズレ | (潤滑より先に固定是正) | 増し締め→芯出し→必要ならライナー更新 |
| ブーン/ビリビリ | ボックスカバー | 増し締め+制振 | 外周固定→制振シート |
| ゴロゴロ(上部) | 軸受 | リチウム#2/VG150~220 | 給脂→異音続けばベアリング点検 |
| チェーン鳴き | チェーン | チェーンオイル | 拭き清掃→浸透→余剰拭き |
| 歯飛び・反転 | チェーン・センサー | まず調整・清掃 | 張り調整・センサー清掃/油は二の次 |
関西でのコスト感と段取り
1. 参考費用(税別)
- 清掃→薄膜潤滑(1面):5,000~15,000円
- 軸受給脂(点検含む):8,000~20,000円
- ライナー更新+芯出し:15,000~40,000円/枠
- チェーン整備(張り・給油):10,000~25,000円
- ボックス制振:10,000~30,000円/基
2. 段取りの鉄則
- 清掃→診断→適正油→量→余剰除去を崩さない。
- 写真台帳を残す(次回判断が楽)。
- 季節前(黄砂・台風)に先回りが原則。
よくある質問(FAQ)
Q1. 市販の“556”で代用できますか?
A. いいえ。埃を抱き込み、摺動部が重く・うるさくなります。レールは無溶剤シリコン薄膜を“ごく薄く”。
Q2. グリスはどれも同じに見えるのですが……
A. 増ちょう剤・基油・硬さが全く違います。リチウムは汎用、カルシウムスルホネートは耐水・防錆・EPが強い等、用途で選ぶのが正解。
Q3. 食品工場ですが大丈夫?
A. NSF H1準拠の食品機械用グリスを選定。滴下・飛散を抑える施工が必要です。
Q4. 低温(冷凍庫前)で朝だけ重い。
A. 低温用(低粘度)×NLGI#1~#2の軸受グリス、レールは乾式薄膜で朝一の起動性が改善します。
Q5. 防火シャッターの潤滑は?
A. 可燃性塗布・機能阻害に注意。認定構造・所管方針に従い、潤滑可否と油種を確認してください。迷ったら無料相談を。

まとめ|「どこに・どれを・どれだけ」——潤滑は設計です
改めてお伝えしますが、潤滑は“塗ること”ではなく、「どこに・どれを・どれだけ」塗るか適材適所を決める設計行為です。
とりあえず潤滑剤をさしていたら、実際は大きな故障につながる場合もあります。
ぜひこのコラムを参考にして、最適な潤滑剤をご活用ください。
- レール=ドライ薄膜。油・グリスはNG。
- 軸受・ギア・ロック=グリス。用途に応じてリチウム/カルシウムスルホネートを使い分け。
- チェーン=専用オイル。ベルトは無給油が原則。
- 量・手順・周期を守って初めて“長持ち・静音・安全”が揃う。
- 混用NG/パージ必須。切替時は古いグリスの完全除去。
- 関西の環境(塩・黄砂・台風・温湿度差)に合わせ、先回りの清掃・薄膜が効く。
どうしても自分だけでは解決できないと感じたときは、ぜひ「シャッター119」の無料相談・出張見積もりをご利用ください。
“正しいグリス選び”で、シャッターを静かに・軽く・長くします。
【ご依頼の流れ】
- 点検:まず、シャッターの損傷箇所を点検します。
- 見積もり:修理にかかる費用を見積もります。
- 修理:必要な部品を交換し、シャッターを修理します。
- 動作確認:修理後、シャッターが正常に動作するか確認します。
修理は、必ず依頼いただいたお客様とお話し、ご納得いただいた上で開始させていただきます。
「当初の見積もりよりも部品の発注をしないといけなくなりそう」「費用がかかりそう」だと判断した場合は、必ず手を止めて再度ご提案をさせていただきます。
いきなり修理を始めて、修理後にビックリする金額を請求するようなことはございませんのでご安心ください。

この記事の著者

シャッター119 編集部
シャッターに関するお役立ち情報を発信しています。代表の私が長年の経験に基づき、修理費用の目安、業者選びのポイント、日々のメンテナンス方法などを簡潔に解説。シャッターに関する疑問を、スピーディーに解決します。シャッターの修理・交換も「シャッター119」にお気軽にご相談ください♪